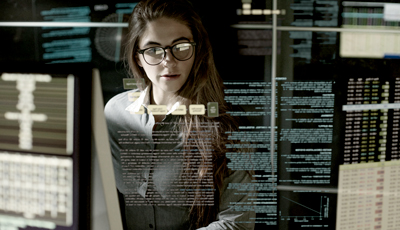マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、マネロン対策等1)を含む金融犯罪対策に官民を挙げて注力する中、2024年6月、犯罪者集団が起業家を装って約4,000もの法人口座を開設し、700億円もの犯罪資金の洗浄を行っていたという衝撃的な報道がなされた。
この集団は、形式上は真正な登記を行った法人として口座開設を申し込み、指南書によって理論武装して審査を潜り抜け、疑わしく見えない普通の人がよどみなく回答することにより対面審査もクリアし、複数の金融機関に多数の法人口座を開設していた。金融業界は、あらためてマネロン態勢の再点検を迫られることになった。
本インサイトでは、マネロン対策等の実務経験豊富な筆者2が、当該事案の概要3を俯瞰した上で、犯罪者集団の跳梁跋扈を許さないためには何が必要かについて私見を述べる。
犯罪者集団の跳梁跋扈を許すな ~法人口座の不正開設を防ぐために~
- リース・クレジット
- 銀行・証券

1 以下断りなく、マネー・ローンダリングとマネロンを同じ意味に用いている。
2 石川慎一郎:日本銀行入行。Big4ファームを経てアビームコンサルティングに入社。この間、大手証券会社において、市場取引の実務に従事した経験を有する。2021年4月、アビームコンサルティングに復職。銀行及び証券会社向けのコンサルティング・サービスを一貫して実施しており、規制対応、リスク管理・コンプライアンス、内部統制構築ならびに当該専門領域に関する監査支援など数多くのプロジェクトをリード。
3 報道をもとにアビームコンサルティングが構成。
-

石川 慎一郎
Director
1.事案の概要とその手口
スタートアップ企業をはじめとするSME4の法人口座管理、なかでも口座の不正開設について考える際には、2024年6月に報道された犯罪者集団リバトングループ(以下、当該集団)による組織的マネー・ローンダリングの事案を看過することはできない。
当該集団は、起業家を装い500社もの法人を設立して約4,000の法人口座を開設。これらの不正口座を利用して少なくとも700億円もの犯罪資金の洗浄を行っていた。不正に口座開設された金融機関はネット銀行のほか、メガバンクや主要行だけでなく地方銀行にもおよび、複数の法人名義で多数の口座が開設されていた金融機関もあった。
マネロン対策等は、メガバンク・グループや主要行等が重点的に対策を講じていれば良いわけではなく、地域金融機関も含め、わが国の金融業界全体で取り組まなければならないことが奇しくも浮き彫りにされた恰好だ。
法人口座は、送金の上限額が個人よりも高く設定されるケースが多く、多額の資金移動が行われても法人間の正規取引を装い易い等、犯罪者から見ると使い勝手の良いマネー・ローンダリングのツールである。金融機関は、犯罪者による口座開設を水際で阻止するため、法人口座の開設に際しては厳しい審査を行っている。
それにもかかわらず、当該集団はIT関連のスタートアップ企業等を装った実態のない法人を登記して設立、「指南書」に沿って銀行の審査を受ける準備をし、これを潜り抜けていた。指南書には、事業内容や社名の由来、口座開設先としてその銀行支店を選んだ理由などの対面審査の想定問答も記載されており、面談によどみなく、スタートアップ企業の経営者として情熱的に答えさせることによってクリアしていた。口座開設役はSNS等を介した闇バイトの募集や口コミで集めていたようだが、スタートアップ企業の創業者であれば経営者然とした風貌である必要はなく、ごく普通の若者であってもおかしくない。これも、不正な口座開設の申し込みを容易ならしめる一因になったのかもしれない5。
当該集団が口座を開設するために金融機関を欺いた手口と、開設した口座の特徴をまとめると、図1の通りである。
 図1 口座開設の手口と特徴
図1 口座開設の手口と特徴
口座開設手口の根幹は、①に記載の通り、形式上は真正な登記を行った法人として口座開設を申し込むことである。
4 Small and Medium-sized Enterprise、中小企業。
5 当該集団が、わが国におけるスタートアップ設立の簡素化という潮流を悪用し、本物のスタートアップ企業に巧妙に紛れたことも、不正な口座開設を容易ならしめる要因の一つになった可能性がある。こうした国や業界をあげた制度改正や新サービスの立上げが行われる際には、本来の目的に反して制度を悪用しようとする者が現れることも忘れてはならない。重要な政策を推進する歩みを止めないためにも、金融機関は十分な対策を講じる必要がある。
2.これまでの金融業界としての対応
当該集団による組織的マネー・ローンダリングが報道によって明るみに出たのは、奇しくも、金融庁が「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」を公表6する直前であった。
この文書では、「第4章.金融サービスの不正利用対策」の中で、複雑化と巧妙化が進む金融犯罪への対策について紹介している。当該対策の四類型と、文書の中における口座の不正取得に関する言及は、図2の通りである。すなわち、口座の不正取得は、法人と個人のそれぞれについて、「新規口座の不正開設」と「既存口座の買入れ・譲受け」に分けることができるが、当該集団の手口の根幹であった法人による不正な新規口座の開設(図2の㋑)に関しては言及されていない7。
 図2 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」における金融犯罪対策の四類型と口座の不正取得への言及
図2 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」における金融犯罪対策の四類型と口座の不正取得への言及
その後、金融庁は「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」において、6項目について金融機関等に対策を要請8しており、それぞれ詳細な対策を示している。そのうち「1.口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化」に関する詳細な対策の種類は、「顧客への周知徹底と理解の促進」、「口座開設時の対策」、「口座開設後の取引モニタリング等」の3つに分類可能である(図3)9。
 図3 「口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化」のための対策
図3 「口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化」のための対策
ここで強調しておきたいのは、当該集団と同じような犯罪者集団は他にも存在しているはずだ、ということである。実際、2025年2月には、2021年1月~2024年5月の4年間で500億円にものぼるSNS型投資詐欺の犯罪収益を洗浄したとして、3名が逮捕されたことが報道された10。この3人は中国やベトナムなどに拠点を置く詐欺グループと中国語でやり取りしていた11。この集団も、法人口座を中心に約300もの口座を管理してマネー・ローンダリングを行っていた12。
したがって、当該集団の手口の根幹である「形式上は真正な登記を行った法人による口座開設」への対応のためにも、「口座開設時の対策」強化はもとより、「顧客への周知徹底と理解の促進」を、第一義的な目的である「顧客とのトラブル防止」だけでなく、「不正な口座開設を謀る者に対して、口座開設時の対策を強化していることを知らしめて牽制する」目的にも活用し、金融業界を挙げて対策の強化を図っていかなければならない。
6 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題(2024年6月)」(2024(令和6)年6月28日、金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/amlcft/20240628/01.pdf
7 法人の代表者の本人確認を除く。
8 「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」(2024(令和6)年8月23日、金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240823/20240823.html
の中で、下記の6項目について金融機関等に対策を要請。
1.口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化
2.利用者側のアクセス環境や取引の金額・頻度等の妥当性に着目した多層的な検知
3.不正の用途や犯行の手口に着目した検知シナリオ・敷居値の充実・精緻化
4.検知及びその後の顧客への確認、出金停止・凍結・解約等の措置の迅速化
5.不正等の端緒・実態の把握に資する金融機関間での情報共有
6.警察への情報提供・連携の強化
9 注8に記載した文書の添付ファイル
「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について(概要)」
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240823/20240823.pdf
10 事案の概要は、報道をもとにアビームコンサルティングが構成。
11 海外からの投資条件緩和、居住条件緩和により投資と人材の誘致が進めば、招かざる国際的な犯罪ネットワークの構築を許すリスクも高まる。重要な政策の本来の目的である正当な投資と人材の誘致を推進するためにも、金融機関は十分な対策を講じる必要がある。
12 これらの口座は3人が直接開設したものではなく、法人口座を売買する「道具屋」と呼ばれるグループから買い取っていたようであるが、道具屋の“品揃え”には、架空の法人を設立し不正に口座を開設する手口が含まれていることが推定できる。「口座の買入れと譲受け」に加えて、「形式上は真正な登記を行った法人として口座開設を申し込む」がマネロンの主たる手口に加わったという見方を変えるべきではない。
3.犯罪者集団の跳梁跋扈を許さないために
当該集団のような犯罪者集団の跳梁跋扈を許さないためには、何が必要であろうか。それは、情報の統制と限定水域における共有(金融業界内の情報共有、および官民の情報共有)である。
-
(1)
犯罪者集団に知恵をつけさせないための情報統制
逆説的ではあるが、官民を挙げたマネロン対策等の進展に伴い、当局を含めた金融業界が発出する対策情報が犯罪者集団に手口のヒントを与えている可能性は否定できない。
例えば、当該集団の指南書には、「口座開設先としてその銀行支店を選んだ理由」が想定問答として記載されていたようだが、これが報道によって明るみに出るちょうど一年前に金融庁が発出した文書13には、地域金融機関において取組が進んでいる事例として「店舗の所在地との地縁の有無等を法人顧客の口座開設における判断基準の一つとしている。」が紹介されている。
こうした情報共有は犯罪者集団に対する牽制にも繋がるため、具体的な情報や事例をどこまで共有するかは難しい問題ではあるが、手口のヒントとなるような情報は可能な限り金融業界内の「限定水域」で実施すべきである。 -
(2)
金融業界内の限定水域における情報共有
全銀協では、2024年12月26日に「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」を立ち上げ14、金融機関の間で不正利用口座の情報を共有する枠組みの構築を検討してきた。その後2025年3月31日に「不正利用口座の情報共有に関する報告書(2024年度)(概要)」15を公表し、金融機関(情報共有元)が検知・凍結した犯罪者の口座情報を金融機関全体へ即時に共有し、共有を受けた各金融機関は共有された情報を活用して犯罪者の口座へ送金していた被害者の口座を検知し、被害者へ連絡して詐欺被害の拡大を防ぐ枠組みの構築に向けて、実務、法令、システムに係る論点について議論した旨、報告している。個別の金融機関が検知できる情報には限りがあるため、不正利用された口座への入金経路や出金先について、金融機関同士での情報共有が可能となれば、口座の不正利用に対するわが国全体の防御力を格段に向上させることが可能になる。
今後は、共有する情報の内容に関して、取引モニタリングに活用するための「検知・凍結した犯罪者の口座情報」の共有に加えて、「疑わしい取引の届出に関する情報」の金融機関の間での共有、こうした情報の可及的速やかな共有の枠組の構築も検討すべきである。
ただし、当該情報共有の範囲や条件などは、共有の目的に照らして、慎重に検討しなければならない。また、個人情報やプライバシー保護と関係する法的な課題16や、情報の質(正確性・最新性の確保と保証)や情報の形式(データ様式やプロトコルの相違)の問題といった解決すべき実務的な課題は多い。 -
(3)
官民の限定水域における情報共有
口座の不正利用に対するわが国全体の防御力を更に向上させるためには、金融当局と金融機関の間の情報共有に加えて、捜査機関と金融機関の間の情報共有の強化が不可欠である。これについては、2025年4月、政府の犯罪対策閣僚会議が「国民を詐欺から守るための総合対策」17を改定し、「法人口座を含む不正な口座情報等について、警察と預金取扱金融機関における迅速な情報共有に係る取組を推進する」18ことが謳われている。金融機関等と捜査機関の間の情報共有はこれまでも行われてきたが、これがさらに強化される恰好だ。
こうした取り組みの推進により、口座の不正利用に対するわが国全体の防御力が向上することを願ってやまない19。
当該集団の手口の根幹であった「形式上は真正な登記を行った法人による口座開設」を防ぐためには、情報の統制と限定水域における共有を推進することにより、官民一丸となって口座の不正利用に対するわが国全体の防御力を向上させる必要がある。これによって、国や業界をあげた制度改正や新サービス立上げ等の悪用を巧妙に謀る者に総合力で対峙し、制度改正などの重要な政策を推進する歩みを鈍らせることなく、犯罪を抑止していくことが重要であると考える。
13「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2023 年6月)」(2023(令和5)年6月30日、金融庁) https://www.fsa.go.jp/news/r4/20230630/20230630.html
14「「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」の設置について」(2024(令和6)年12月26日、一般社団法人全国銀行協会) https://www.zenginkyo.or.jp/news/2024/n122601/
15「「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」報告書について」(2025(令和7)年3月31日、一般社団法人全国銀行協会) https://www.zenginkyo.or.jp/news/2025/n033101/
16 “金融機関の守秘義務を基にした上で、国民を詐欺から守る”という情報共有の目的と、“個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守る”という個人情報保護の目的との間に、本質的な利益相反は生じないと考える。情報共有を可能とする法的な手当てを期待したい。
17 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(2025(令和7)年4月22日、犯罪対策閣僚会議)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/250422/honbun-1.pdf
18 注17の文書 「1 SNS型投資・ロマンス詐欺対策」、「(4)金銭等の交付段階への対策」、「ア 被害の未然防止及び拡大防止のための取組」、「(ウ)預金取扱金融機関におけるモニタリングの強化」
19 同文書では「口座の悪用を牽制するため、捜査機関等が管理する架空名義口座を利用した新たな捜査手法や関係法令の改正を早急に検討する」ことも謳われている。取り組みの抜本的な強化が期待される。(注17の文書、「1 SNS型投資・ロマンス詐欺対策」、「(4)金銭等の交付段階への対策」、「イ 被害金の追跡及び被害回復を容易にするための取組」、「(イ)架空名義口座捜査等の新たな捜査手法の導入に向けた検討」)
4.アビームコンサルティングの取り組み
アビームコンサルティングではこれまでも、金融当局や銀行の一線でマネロン対策等を行う実務者をスピーカーに招き、金融犯罪対策とAMLに関するセミナーを主催20する等、金融機関間の情報共有の枠組み検討や、官民連携をご支援する活動にも積極的に取り組んで来た。
それに加えて、アビームコンサルティングは、これまで多くのクライアントとともに培ってきた金融犯罪対策の知見、総合コンサルティングファームとしてのテクノロジーや組織運営、戦略策定に関する知見を豊富に有している。今後も引き続き、金融機関向けのコンサルティング支援を通じて実務的な課題解決を推進するとともに、金融機関による安心・安全な金融サービスの提供に貢献したいと考えている。
20 弊社インサイト「金融犯罪対策/AMLの今と未来~金融機関に求められる新たな視点とは~」
https://www.abeam.com/eu/ja/insights/081/
相談やお問い合わせはこちらへ