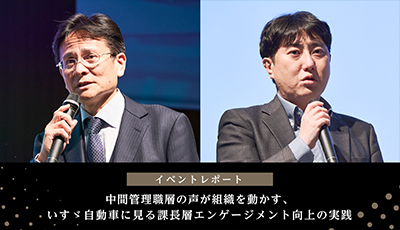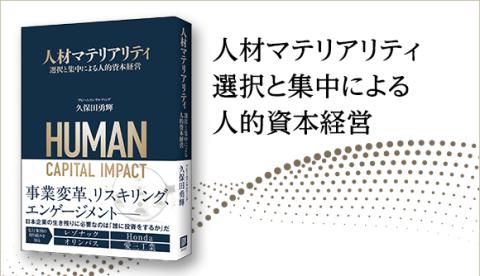IT・AIの急速な進展や脱炭素化、環境問題への対応といった外部環境の変化により、企業は事業ポートフォリオの抜本的な見直しを迫られている。そうした状況下、変革を支えるのは「人材」であり、特定の高度なスキルを有する人材だけでなく、既存業務を支える熟練人材、新領域を切り拓く柔軟な人材など、多様なスキル・経験をもつ人材をいかに最適に活用するかが求められている。一方で、労働供給の制約や報酬の上昇により人材獲得競争は激化しており、スキルのアンマッチが発生する人材配置は企業経営にとって大きなリスクとなり得る。こうした中、注目されているのが、「人材ポートフォリオ」である。
本インサイトでは、人材ポートフォリオの概念や作成方法など、人材ポートフォリオの構築・運用を通して、いかに持続可能な成長に向けた基盤を構築するかについて、事例を交えながら解説する。
人材ポートフォリオとは?作成方法や重要性が増している理由、企業事例を解説
- 経営戦略/経営改革
- 人的資本経営

-

淺見 伸之
Principal -

細田 俊之
Senior Manager
人材ポートフォリオとは
人材ポートフォリオとは、企業が経営戦略や事業戦略を効果的に実現するために、必要な人材を「量」と「質」の観点から体系的に可視化・分析するためのフレームワークである。
ここでいう「量」とは、各組織や業務・役割ごとに必要な人員数(ヘッドカウント)を指す。たとえば、営業部門に何人の人材が必要であるか、開発部門にどの程度のエンジニアを配置すべきか、といった観点から、人材の適正な配置人数を定量的に把握することが求められる。
一方、「質」とは、各役割に求められるスキルや専門知識に対し、現在の人材がどれだけ充足しているかを評価する指標である。これは単に資格の有無や経験年数のみを確認するものではなく、現場における実践力、リーダーシップ、デジタルスキルといった多面的な能力を含めて捉える必要がある。
人材ポートフォリオを作成することで、各事業や組織ごとに、どの役割に何人の従業員が従事しているか、スキルの熟達度がどの程度かを一目で把握することができる(図1)。たとえば、ある組織の構成が、熟達者中心なのか、スキル不足の人材が多いのかといった状況を瞬時に捉えることも可能になる。人材ポートフォリオは、企業が持続的に成長するための、人材マネジメントの可視化と最適化を実現する重要なツールと言える。
また、人材ポートフォリオは、単なる人材情報の整理にとどまらず、戦略的な意思決定やキャリア形成を支える基盤として、以下のようなメリットをもたらす。ここでは、経営・事業・従業員の3つの視点から整理する。
- 経営の視点:キー人材のスキル充足状況や、組織ごとの生産性の把握が容易になる
- 事業の視点:人材の採用・配置・育成を、単なる人数ではなく「スキルの質」という観点から検討できる
- 従業員の視点:企業や事業が求めるスキル像が明確になることで、自身とのギャップを認識し、自律的なキャリア形成に向けた能力開発に踏み出す契機となる
動的人材ポートフォリオとは
動的人材ポートフォリオとは、企業の経営戦略やビジネスモデルの変化に応じて、必要な人材の質と量を柔軟かつ迅速に再配置・再構築する仕組みを指す。これは、適所適材・適時適量の人材配置を実現するための戦略的な人材マネジメントの枠組みである。
この概念は、経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」において、人的資本経営を実現するための5つの共通要素の一つとして位置づけられ、その重要性が強調されている。企業が持続的な成長を遂げるためには、経営戦略と連動した人材戦略の策定と実行が不可欠であり、動的人材ポートフォリオはその中核をなすものとされている。
しかしながら、経済産業省が実施した「人的資本経営に関する調査(2022年)」によると、企業における動的人材ポートフォリオの取り組みは、他の人的資本経営の要素と比べて最も進捗が遅れていると報告されている。
さらに、2024年の調査では、人材ポートフォリオの作成に関する課題として、59%の企業が「中長期的に求められる人材の質と量を把握できていない」、31%が「現在の人材の質と量を把握できていない」と回答している。
これらの結果からも、人材ポートフォリオの作成は多くの企業にとって、いまだ大きな課題であることが明らかとなっている。
関連インサイト:人的資本経営の実現に向けた「動的人材ポートフォリオ」の構築方法
人材ポートフォリオの重要性が増加している理由
近年、人材ポートフォリオの重要性が飛躍的に高まっている。その背景には、企業を取り巻く外部環境の急激な変化とともに、経営・事業・従業員の三者それぞれの視点からの要請が複合的に重なっていることが挙げられる(図2)。
こうした中で、人材ポートフォリオは、もはや人材管理の枠にとどまらず、人的資本経営の中核を支える戦略的なツールとしての役割を担うようになっている。
ここでは、人材ポートフォリオの重要性が高まっている理由を、主な3つの観点から整理する。
1.人材版伊藤レポートに端を発した「人的資本経営」への注目
「人的資本経営」という概念は、2020年に経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート」を契機に大きく注目を集めるようになった。このレポートでは、企業が中長期的に持続的な成長を遂げるためには、人材を財務資本と同様に“資本”として捉え、戦略的に投資・活用すべきであることが明確に示されている。
特に、企業に事業ポートフォリオの見直しが求められる中で、変革を実行する主体として「人材」に注目が集まり、そのマネジメントのあり方が経営の本質的課題として位置づけられている。この人的資本経営を実現するためのカギとして、人材を質・量の両面から可視化し、戦略的に配置・育成する仕組みである「人材ポートフォリオ」の整備の必要性が強調されている。
さらに、2022年に発表された「人材版伊藤レポート2.0」では、「動的人材ポートフォリオ」が、人的資本経営を構成する5つの共通要素の一つとして明記され、企業変革における重要性が再確認された。
2.ISO30414への適応
ISO30414とは、人的資本に関する情報開示の国際標準規格であり、企業が人的資本の重要な指標を社外に開示する際の指針である。人的資本経営が注目される中、この規格は、企業の取り組みに対する透明性や信頼性を担保するフレームとして機能しつつある。
しかし、単に人材関連の指標を断面的に数値で開示するだけでは、企業の本質的な取り組みを十分に伝えることはできないだろう。重要なのは、事業ポートフォリオの変化に合わせて理想の人材ポートフォリオ(あるべき姿)を描き、現状との差(ギャップ)を明確化し、施策につなげるという“変革ストーリー”を構築することである。
ISO30414の指標は、このストーリーの進捗を定点観測するためのツールとして活用すべきものと言える。単なる指標の羅列ではなく、戦略と整合した文脈の中で、企業の意図と方向性を示す形で開示することが、社内外のステークホルダーにとって真に意味のある情報となる。
3.ビジネス環境の変化とVUCA時代への対応
人材ポートフォリオの必要性を高めているもう一つの要因は、ビジネス環境そのものの変化が激しさを増していることである。テクノロジーの進展、脱炭素やESGへの対応、地政学リスクの高まりなど、企業が直面する外部環境は日々変化している。
このような環境は、まさに「VUCA(ブーカ)」の時代と呼ばれる。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、未来の予測が困難な状況を表す。
VUCA環境下では、従来のように固定的な組織・人材構成では変化に対応できず、戦略と連動し、柔軟に再構築される人材ポートフォリオが不可欠となる。スキルの陳腐化も早まる中で、必要なスキル・経験を継続的にアップデートし、最適に配置していく仕組みが、企業の競争力を支える基盤となる。
このように、「人的資本経営」への注目、国際基準への適応、そしてVUCAという不確実な経営環境への対応という3つの視点から、人材ポートフォリオの重要性は急速に高まりを見せている。企業が変化に適応し、持続的な成長を遂げるためには、人材ポートフォリオの構築・運用こそが、人材戦略の中核であるべき時代を迎えていると言えるだろう。
人材ポートフォリオを作成するメリット
これまで紹介してきた通り、人材ポートフォリオの作成は、単に人材情報を可視化するだけにとどまらず、経営・事業・従業員の三者それぞれにとって実践的なメリットをもたらす重要な手段である。
ここでは、経営・事業・従業員の3つの観点から、人材ポートフォリオを作成するメリットを紹介する。
1.経営の観点:将来課題の予測と早期対処
経営層にとっての最大のメリットは、将来の人材リスクを先読みし、手遅れを防ぐことができる点である。人材ポートフォリオを作成・活用することで、現在の人材構成を年齢、役職、性別、雇用区分、報酬などの切り口で詳細に可視化し、さらに退職率・採用数・昇進速度などのデータを活用して、“成り行き”の将来人材ポートフォリオ(現状を延長した未来)を描くことが可能になる。
その“成り行き”の姿と、戦略実現のために必要とされる理想的な人材ポートフォリオ(あるべき姿)との間にあるギャップを明らかにすることで、どのような人的課題が生じるかを具体的に特定できる。これはアップスキル・リスキルといったスキル開発だけでなく、リテンション施策、女性活躍、管理職の後継層不足など、人材にまつわる複数のリスクや課題を網羅的に発見することができるという大きな意義を持つ。
2.事業の観点:配置と育成の精度向上
事業部門においては、常に必要な人材の「量」と「質」が十分に揃っているとは限らない。限られたリソースをどう組み合わせ、最適な布陣を構成するかは現場の大きな課題である。人材ポートフォリオの活用により、人材の不足しているスキルや重複する役割が明確になり、経験や勘に頼った属人的な配置や育成から脱却できる。
また、人材ポートフォリオ上で可視化されたスキルや役割要件が、事業と従業員の共通言語となることで、個別育成の目標もより具体的になる。曖昧だった育成方針から、スキルベースでの育成計画へと転換し、成果につながる教育投資が可能となるだろう。
3.従業員の観点:キャリア選択肢の明確化と自律支援
従業員にとっても、人材ポートフォリオの存在は自律的なキャリア形成を支援するインフラとなる。人材ポートフォリオの作成を通じて、事業が求める人材像が明確に定義され、必要なスキルや知識が可視化されることで、キャリアの選択肢が現実的にイメージしやすくなる。
たとえば、今の職務で専門性を深めるキャリア、あるいは新たな領域へ挑戦して異なる専門性を獲得するキャリアなど、従業員が主体的に未来を選ぶための「地図」と「選択肢」が提供されることになるからだ。
このように、人材ポートフォリオは、経営にとっては戦略実行の前提となる課題の特定手段であり、事業にとっては限られた人材を最大限に活かす設計図であり、従業員にとってはキャリアを描く羅針盤となる(図3)。まさに、人材ポートフォリオは、事業戦略・人材戦略・従業員のキャリア形成を一体化するための橋渡しとなる重要な仕組みなのである。
人材ポートフォリオを作成する5つのステップ
人材ポートフォリオは、事業戦略と人材戦略を結びつける「設計図」のような存在であり、その作成には一貫したステップを踏む必要がある。単に人材情報を集めるだけではなく、「どの職務に、どんなスキルを持った人材が、どのレベルで従事しているか」を構造的に捉えることが求められる。
ここでは、人材ポートフォリオを構築するための実践的な5つのステップを紹介する。
1.職務の定義(人材の量の可視化)
最初に行うべきは、各組織において従業員が担っている役割を「職務」として明確に定義することである。「職務の定義」は、従来の日本で多いメンバーシップ型雇用においても、業務分掌や役割分担の情報をもとに行う必要がある。
ここで重要なのは、「職務をどの粒度(細かさ)で定義するか」という視点である。たとえば、「営業職」と一口に言っても、扱う商材(製品かサービスか、既存商品か新製品か)、担当する顧客層(大企業向けか中小企業向けか、法人か個人か)によって、実際の仕事内容や求められるスキルは大きく異なる。このような場合には、「法人向け新規営業」「中小企業向けルート営業」など、職務を細分化して定義することが有効である。
一方で、取り扱う商材が異なっても、求められるスキルや業務の性質がほぼ共通している場合には、あえて統合して一つの職務として定義するという判断もあり得る。たとえば、製品知識の違い以外に業務内容や商談プロセスがほぼ同じであれば、「営業(汎用)」として横断的にまとめた方が、組織横断での分析や配置検討がしやすくなる。
あまりに各部門ごとに詳細な定義を追求しすぎると、過剰な細分化に陥り、全体最適を損なう恐れがある。そのため、職務定義は個別最適ではなく、全社的な視点で俯瞰的に設計することが重要である。
2.担当者の確認(人材の量の可視化)
次に、定義した職務に対して、実際にその業務を担っている従業員を整理する。この際、兼務などの要素を考慮し、担当割合も含めて整理することが重要になる。これにより、どの職務にどれだけの人的リソースが割かれているかを明確に把握することができる。
3.スキルの定義(人材の質の可視化)
そして、職務ごとに、求められる人材像や人材要件を定義していく。ここでのポイントは、その職務において「自社の強み・特徴は何か」「どのスキルが不可欠か」を組織側が的確に捉えることである。
スキル定義にあたっては、職務遂行に必要となるスキルを洗い出し、それぞれに対して必要な習熟度(スキルレベル)を設定する。この際、以下のような2段階の水準設定を行うのが望ましい。
-
a.
模範人材(自律的な職務遂行に加え、専門領域に関する深い知識・知見をもとに社内外にリーダーシップを発揮できる人材、ロールモデル)に求められるスキルとレベル
-
b.
即戦力人材(自律的に業務を遂行できる一人前の人材)に求められるスキルとレベル
そのうえで、従業員の保有スキルを可視化し、即戦力として求められる水準に達していない場合は、スキルの充足状況に応じて「ポテンシャル人材」または「要強化人材」として判定する。また、全社的に展開することを想定して、同じスキルでも職務の違いによって求められるレベルを調整しつつ、横断的に比較できるフレームワークを整備することが重要になる。
4.スキルの評価(人材の質の可視化)
続いて、従業員が実際にどのスキルをどのレベルで発揮しているかを評価する。評価のポイントは、等級にもとづく人事評価ではなく、発揮された行動・成果にもとづく絶対評価であること指す。
この評価は、昇格・昇進と直結させるものではなく、戦力把握・人材配置・育成方針の策定を目的とするものである。これにより、従業員本人にとっても納得感が高く、成長支援につながる評価となる。
5.職務遂行レベルの判定(人材の質の可視化)
最後に、従業員ごとに職務ごとのスキル充足状況をもとに、職務遂行レベルを判定する。これにより、個々の人材を以下のようなカテゴリに分類することが可能になる。
- 模範人材(スキル定義の最上位基準を満たす)
- 即戦力人材(業務を自律的に遂行可能)
- ポテンシャル人材(一部基準に達しているが今後の成長に期待)
- 要強化人材(スキル充足が不足しており、育成や支援が必要)
この分類により、現場と人事の間で共通の理解が形成され、的確な配置・育成・支援の実行につなげることができる。
この5つのステップを踏むことで、単なる情報の集約ではなく、実際に意思決定・施策立案に活用可能な「戦略的な人材ポートフォリオ」を構築することが可能となる。これにより、企業は自社の戦略実行に必要な人材像を明確化し、人材の最適配置と育成を通じて、持続的な競争力を築くことができるのである。
人材ポートフォリオ作成の注意点
人材ポートフォリオの作成には、精緻さよりもスピード、現場との協働、そして多様な切り口による実用性が重要となる。継続的に活用される仕組みとするためには、完璧な定義を目指すよりもまず実行し、運用しながら調整していくアプローチが有効と言える。本章では、人材ポートフォリオを構築・運用する上で留意すべき3つのポイントを整理する。
1.スピード重視の定義と柔軟な運用
人材像やスキルの定義は、緻密さを追求するあまり時間をかけすぎると、事業環境の変化や重要人材の離脱など、変動リスクへの対応が後手に回る恐れがある。実際、丁寧に設計されたアウトプットが現場で活用されないまま陳腐化してしまうケースも少なくない。したがって、まずは迅速に定義を行い、トライアル運用を通じて得られるフィードバックをもとに随時調整していくことが肝要となる。
その際、アビームコンサルティングでは、マーサージャパン株式会社が提供するスキルライブラリなどの外部リソースを活用して迅速な立ち上げを支援するアプローチを推奨している。ゼロからスキル定義を構築するよりも、信頼性のあるテンプレートを起点に、必要に応じてカスタマイズすることで、精度とスピードの両立が可能になる。
関連ソリューション:人的資本経営における評価指標の管理・分析や人材情報の統合管理を実現するSaaS型プラットフォーム「ABeam Human Capital Platform」
2.組織横断的な協働体制と段階的展開
人材ポートフォリオの作成は、各部門への負荷が一定発生する活動ではあるが、中・長期的な成長に向けて、一過性の取り組みではなく、継続的な運用が前提となる。したがって、単なるトップダウンでは定着せず、事業部門・管理部門の責任者と対話を重ねながら、納得感を持って進めることが重要となる。
特に初期段階ではPoC(概念実証)として特定組織で有用性を検証し、課題解決のロードマップを提示した上で、全社展開へと発展させるステップが現実的である。このプロセスには、人事部門だけでなく、経営企画部門や事業部門との共同推進体制の構築が不可欠である。人材戦略を組織全体の戦略に連動させるためにも、多様なステークホルダーを巻き込んだ推進体制を整える必要がある。
3.多面的な切り口による企業独自の設計
これまでご紹介してきた通り、人材ポートフォリオは、単にスキルの有無だけで構成されるものではない。スキルはあくまで基盤情報の一つであり、年代・性別・報酬・エンゲージメントなどの属性情報を組み合わせることで、より現実的で有効な人材像を浮かび上がらせることができる。
このように、設計においては、企業ごとの戦略・課題に即したカスタマイズ設計が不可欠になる。他社の事例を参考にすることは一定有効ではあるものの、それをそのまま模倣するだけでは十分な効果は得られないだろう。自社固有の組織文化や経営課題にフィットした「自分たちの人材ポートフォリオ」を構築する意識が重要となる。
人材ポートフォリオ活用の企業事例
最後に、持続的な成長を実現するために、人材の可視化と最適活用に取り組む企業の事例を紹介する。
あるメーカーでは、複数の事業セグメントの下に、さらに複数のユニット・事業部を持つ構造を採用していた。これまで各事業部が個別最適を追求し、優秀な人材への依存を前提に成長を遂げてきたものの、事業部間の連携不足や情報共有の欠如が組織の硬直化を招いていた。
この状況に対し、経営陣はこのままでは「事業の持続性が危うい」との危機感を強め、人材ポートフォリオの導入に着手した。
現在、導入は一部の部門においてトライアル的に進められており、その過程で既に一定の効果が現れ始めている。具体的には、事業部間で共通の人材像やスキル要件を定めたことで、従業員を部門横断的に把握する視点が生まれ、従来の個別最適な人材配置から脱却する動きが進みつつある。
また、スキルの充足状況を可視化したことで、人材育成を阻害していた「経済価値の最大化」のみに偏った評価制度の課題が浮き彫りとなり、評価のあり方や育成方針の見直しに向けた議論が加速している。こうした動きを受けて、現在は全社展開に向けた取り組みが本格化しており、人材ポートフォリオを軸にした戦略的人材マネジメントへの転換が着実に進められている。
人的資本経営を支えるSaaS型プラットフォーム「ABeam Human Capital Platform」
人的資本経営を実効性のあるものとするためには、人材情報を統合的に管理し、求める人材像に対するスキル充足状況を可視化する仕組みが不可欠になる。特に、人材ポートフォリオの構築においては、スキルの保有状況に応じて職務レベルを自動で判定し、組織全体の傾向やバランスを把握できるプラットフォームが求められる。
従来のタレントマネジメントシステムは、個人単位でのスキル管理には強みがある一方、組織全体のスキル充足状況にもとづく職務レベルの判定やポートフォリオ表示といった視点での分析には限界があった。また、BIツールはデータの可視化には優れているものの、評価ロジックやビジネスルールを実装して、求める人材像とのギャップを明示するような設計には不向きである。
こうした既存ツールの限界を補い、戦略的人材マネジメントの実現を支援するために、アビームコンサルティングはSaaS型プラットフォーム「ABeam Human Capital Platform」を独自に開発した(図4)。このSaaS型プラットフォームは、人的資本経営に必要な評価指標の管理・分析機能と、組織全体のスキル充足状況にもとづく人材ポートフォリオの構築・活用を一体的に支援する。
職務ごとに求められるスキルや習熟度をあらかじめ定義し、それに対する従業員のスキル保有状況をもとに、即戦力人材や模範人材といった職務遂行レベルを自動で判定。これにより、育成対象の明確化や配置の最適化、組織単位でのリスク把握など、全社的な人材戦略立案が可能となる(図5)。
既存のタレントマネジメントシステムを活用しながら、短期間でデータ統合・可視化ができるため、人材領域における諸施策の評価指標(KPI/KGI)の管理・分析や人材情報の統合管理を検討されている企業ご担当者の方にはぜひ活用をご検討いただきたい。
関連ソリューション:人的資本経営における評価指標の管理・分析や人材情報の統合管理を実現するSaaS型プラットフォーム「ABeam Human Capital Platform」
人材ポートフォリオを理解するための書籍
ここまで、人材ポートフォリオの作成方法や注意点などを紹介してきたが、より詳細に知りたい方には、アビームコンサルティングが出版した「人材マテリアリティ 選択と集中による人的資本経営」をお勧めしたい。
本書は、人的資本経営を実現するうえで欠かせない「人材ポートフォリオ」の重要性とその活用方法について、実務に即した視点から丁寧に解説した一冊である。経営戦略における成長領域や人材課題(人材マテリアリティ)を見極め、限られた人的リソースの中で「選択と集中」によって人材投資を行うという、人的資本経営の中核的アプローチを体系的に示している。
また、実際に企業で行われた取り組み事例も豊富に紹介しているため、人的資本経営に取り組む経営層・人事部門だけでなく、戦略的人材マネジメントを志向する企業の方にぜひ手に取っていただきたい。
まとめ ~事業変革に資する人材ポートフォリオの構築に向けて~
人的資本経営への注目が高まる中で、人材ポートフォリオは単なる人材管理の枠を超え、経営・事業・従業員の三者をつなぐ重要な基盤としての役割を担いつつある。特に、急速に変化するビジネス環境においては、現状を可視化するだけでなく、将来を見据えた「動的人材ポートフォリオ」の構築が不可欠になる。
この動的なアプローチにより、将来の人材ギャップを予測し、戦略的な育成や配置、リテンション施策につなぐことができる。持続的な事業成長を支える人材戦略の実現に向けて、人材ポートフォリオの活用は今後さらに広がっていくだろう。
アビームコンサルティングでは、こうした課題に対応するための独自フレームワークと、構築・運用を支援するSaaS型プラットフォーム「ABeam Human Capital Platform」を提供している。
人材情報の統合管理から、スキル充足度にもとづく職務レベルの判定まで、人的資本経営の実行を支える実践的なプラットフォームをはじめ、伴走型の支援を通して、人的資本の高度化に向けた企業変革を力強く後押ししていきたい。
相談やお問い合わせはこちらへ