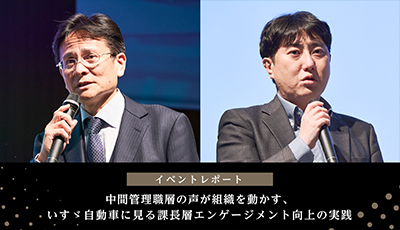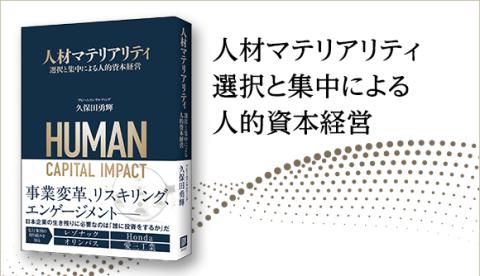日本の労働生産性はOECD諸国の中でも下位クラスに低迷しており、経済成長の大きな制約要因となっている。さらに少子高齢化の進行によって労働力人口が減少する中、限られた人材を有効活用し生産性を向上させることが、日本企業にとって喫緊の課題である。
ところが、日本の労働市場は流動性が低く、メンバーシップ型雇用(終身雇用・年功序列)に根差しているため、欧米で一般的なジョブ型(職務明確化)などの人材マネジメント手法をそのまま導入しても十分に機能しにくい実態がある。
本インサイトシリーズ(全6回)では、日本企業特有の構造問題を解決する新たなマネジメントモデルとして、「ケイパビリティ型人材マネジメント」について解説する。
第1回では、日本企業が直面する低生産性と人材の需給ギャップの現状や、「ケイパビリティ型人材マネジメント」のアプローチについて紹介する。