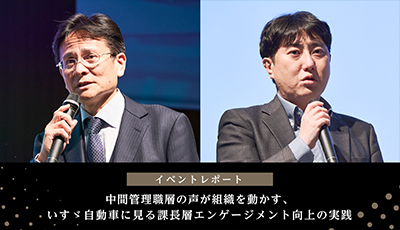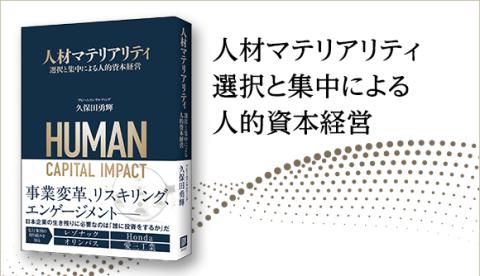先述した「タレントポートフォリオマネジメント」の中でも、特に重要な課題として、2番目の「ジョブを介した社内労働市場の流動化」があると、浅見は指摘。その理由として、「二律背反的なステークホルダー同士のアンマッチを防ぎながら、社内人材の流動化を加速する仕組みづくりは、人事部門にとっても非常に悩ましい課題」である点を挙げる。
また、この背景について江口氏は、これまでは3者間の共通言語がないまま、それぞれが希望を主張する状態が続いていたと分析。「今後はジョブを共通言語とすることで、必要な仕事と人材情報を正確に可視化し、配置の妥当性を3者が客観的に把握できる環境をつくり出す試みが必要」と語る。
これを受けて淺見は、その実現に必要な4つの課題を提起する。
第1の課題は、「ジョブやスキルを共通言語として理解し、対話可能なものに整理していくこと」である。これまでの人材起点で「特定の人のためのポジション」をつくるのではなく、シビアなほど公平に明文化することが重要だ。
第2の課題は、経営と事業が合意するための対話を、人事部門がどうサポートしていくかだ。「とりわけHRBPには、市場環境と成長戦略を前提に、要員計画の変化と打ち手を一連のストーリーとして経営に示し、対話できるかが問われる」と、江口氏は言う。
第3の課題は、「ジョブマッチングの実効性向上」である。とはいえ、最初から完全に要件を満たす人材はいないので、マストスキルと配属後に育成可能なスキルを分けて考えることが、マッチングの実現可能性を高めるポイントになる。
ここでは、処遇の問題も非常に大きな壁になる。淺見は、「等級制度などがミスマッチやパフォーマンス低下の温床になり得る」と強調する。江口氏も、マッチングに際しては、判断の基準をスキルだけに限定せず、より広く捉える必要があると指摘。「内在的な本人の特性やパーソナリティでのマッチングも、企業によっては進み始めている」と明かす。
そして第4の課題は、「魅力あるジョブの提示と惹きつけ」。すなわち、企業独自の価値提案の強化だ。
「最終的に従業員が企業を選ぶ理由は、ジョブだけでもないし報酬だけでもない。その企業ならではの要素を付加しながら、従業員への提供価値として訴求していくことが重要になっています」(江口氏)