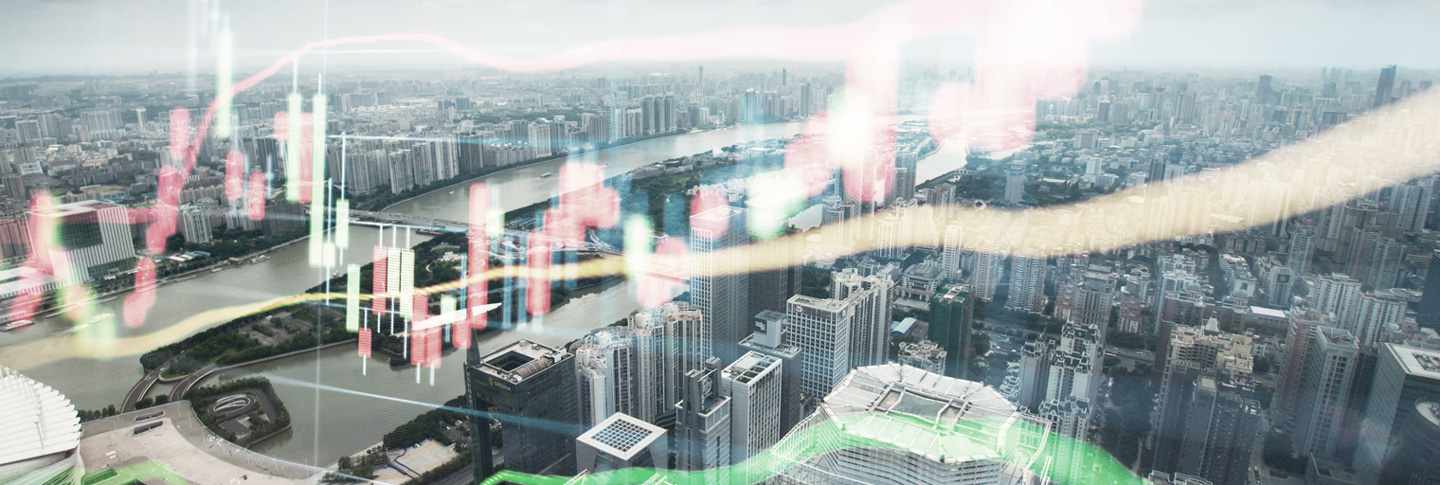1. 役員体制の強化
今回全体で1位になったのが、「役員の平均年齢」であった。柳氏が月刊資本市場2024年7月号で発表した「柳モデルのTOPIX採用全銘柄への適用に係る実証研究の示唆」でも、TOPIX採用全銘柄でPBRに対して有意かつ望ましい関係性が得られた割合が高い分野のTOP3に取締役会構成がランクインしており、経営に新たな風を与えることを目的に役員の多様性が求められていることが伺える。
2. 研究開発における成果
「研究開発による創出製品数」(4位)、「登録特許件数」(16位)のランクインから、研究開発という企業の新たな価値創出と競争力強化に直結する指標が企業価値向上にもつながることがデータ上でも明らかとなった。企業においては研究開発の成果をステークホルダーに対して、適切に開示していくことが求められている。
3. ブランド力の強化
「工場・ミュージアム・ショールームなどの見学来場者数」(11位)や「企業ブランド調査結果」(14位)は、企業価値向上においてブランド力の貢献が大きいことを示している。企業は地域・社会との交流やブランディング活動を実施することで、企業への信頼と評価を高めるとともに競争力につながるブランド力の強化を進めていくことが重要であることがわかった。
4. 従業員エンゲージメントの重要性
所属組織への貢献意欲を示す指標である「従業員エンゲージメント」が25位に新たにランクインしたことから、従業員のプロアクティブな行動や学習意欲が企業の持続的成長に寄与することが示された。高いエンゲージメントは、定着率の向上に加え、従業員の育成および組織の成長につながる。実数値が対外的に開示されることが少ない指標だが、従業員エンゲージメントを高める環境を整えることの重要性が明らかとなった。
5. 投資家とのコミュニケーション
「投資家とのコミュニケーション」に関わる指標として、「投資家との面談回数」(26位)がランクインした。投資家の声に耳を傾けるとともに、投資家からの関心が高い経営の観点に対し質の高いコミュニケーションを多くの投資家と行い、理解を得ることが、成長期待の醸成につながり、企業価値向上に貢献することが確認された。
なお、「研究開発成果」や「ブランド力」関連の指標が上位にランクインしていることから、企業の競争力の源泉となり得る非財務資本を増強することが、企業価値を押し上げ得ることが示されている。