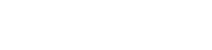これこそが、本質的な「トレードオン(成長と効率の両立)」の財務的な正体である。成長すればするほど、AI資産の減価償却費の比率は下がり、利益率が指数関数的に改善していく。この「非線形な収益構造」への転換こそが、B/S動的再構築のゴールなのだ。
もちろん、営業レバレッジを高めることは、売上減少局面での利益悪化リスク(ボラティリティ)を同時に受容することを意味する。財務の教科書通りであれば、不確実な環境下ではアウトソーシングなどによる「変動費化」で損益分岐点を下げるのが定石だ。
しかし、労働供給が細り、人件費が高騰し続けるこれからの日本において、「人」に依存し続けることこそが、中長期的な経営リスクとなり得る。人件費は今後も上がり続ける「インフレ資産」であり、逆にAIやコンピューティングコストは性能対比で低下し続ける「デフレ資産」である。「インフレする変動費(人)」を「デフレする固定費(AI)」へと切り替える。一般に固定費化はリスクと見なされがちだが、インフレ局面ではむしろ合理的な戦略となる。コスト構造を、外部環境(賃金高騰)の影響を受けにくい「自社保有資産」へとシフトさせることこそが、ボラティリティを抑制し、経営の安定性を担保する「真のガバナンス」となるのである。
人口減少時代にあって、今後、労働力は極めて「希少な資源」となる。その貴重な人材を、AIでも代替可能な「処理業務」に縛り付けておくことは、経営上の損失である。AIトランスフォーメーションにおける人の役割は、以下の2つに再定義される。
- AIスーパーバイザー: AIの出力結果を監査・修正し、品質を担保する「新たな定型業務」の担い手
- ハイタッチ: 顧客対応や現場調整など、AIには模倣できない「人間味」が付加価値となる領域
AI資産(限界費用ゼロ)で量的な効率を担保しつつ、人は人ならではの領域(質的・対人的業務)で価値を発揮する。この「役割分担の再設計」こそが、労働力不足時代を生き抜くための必然的な生存戦略である。
以上のことから明らかなように、AIトランスフォーメーションとは、単なるツールの導入ではない。企業という巨大なシステムを動かす「経営OS(基盤)」そのものを、人海戦術(P/L脳)から資産活用(B/S脳)へと抜本的に書き換える行為である。その成否を握るのは、もはやCIOやCTOだけではない。「人とお金の流れ」を規律づけるCFOとCHROだ。経営会議で問うべきは、「何時間削減できたか」ではない。また、外部のコンサルタントが描いた「バラ色のロードマップ」を承認することでもない。真に問うべきは、「自社のCFOが、効率化配当とゲイン・シェアリングによって何%のリソースを『費用』から引き剥がし、それをどの『資産(OS)』に変換して、PBR向上(営業レバレッジ)にどのように寄与させたか」である。
AIトランスフォーメーションは、硬直化した日本企業のバランスシートを再編するための構造転換のプロセスである。その舵を握り、技術者が生み出した「革新」を財務的な「資産」へと昇華させる権限を持つのは、CFOの決断にかかっているのである。
今後もアビームコンサルティングは、個社の目的や推進ステージに沿ったコンサルティングサービスを提供することで、AI活用による価値創造を加速させ、スピーディーかつ確実な企業変革の実現を支援していく。