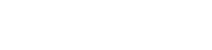今やAIはビジネスにおいて不可欠な存在となり、活用することが当然視される時代である。その一方で、「ROI(投資利益率)の不透明さ」や「現場定着の難しさ」、「PoC疲れ(概念実証の繰り返しによる疲弊)」や「成果が見えづらい」といった課題が顕在化している。こうした背景には、AIを単なる「現場の効率化ツール」として捉え、経営や事業の変革と切り離してしまっている現状がある。AIが事業変革と十分に結びつかないまま導入されると、その価値は限定的となり、期待した成果を生みにくい。
本インサイトでは、経営企画・DX推進・事業変革を担うリーダーに向けて、AIを「価値創造を加速する経営OS(Operating System)*」と再定義し、収益性・成長性・規律性を同時に高める「トレードオン」構造への転換(AIX:AIトランスフォーメーション)と、その実行ロードマップを提示する。
*企業の意思決定・業務プロセス・価値創造を統合的に支える基盤を指す。