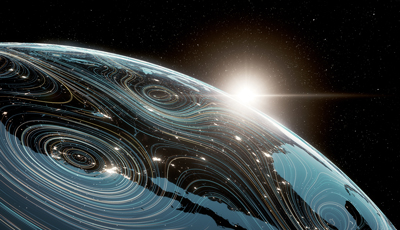気候変動や資源枯渇の深刻化、サステナビリティ経営への関心の高まりを背景に、環境保全と企業の持続的成長を両立するサーキュラー・エコノミー(循環経済)に注目が集まっている。EUでは先進事例もあり関連する法整備も進んでいるが、実現は容易ではない。これまで多くの企業が取り組んできたリサイクルなどの限定的な施策だけではなく、ビジネスモデル自体の変革が求められるからだ。
2025年9月8日に開催された「環境課題解決と収益向上を両立する サーキュラービジネスのすすめ ―トレーサビリティで切り拓く、持続可能な製造―」では、アビームコンサルティング サステナブル戦略SCMユニット サーキュラー・エコノミー エグゼクティブフェローの遊佐昭紀と、Circularise Japan株式会社 プロジェクト・オペレーション・リード 上野浩太郎氏が登壇。循環型ビジネスモデルへの転換に踏み出した企業の最新事例とともに、環境貢献と事業収益性両立のポイントを解説した。
(本稿は、本セミナーを再構成しています。)