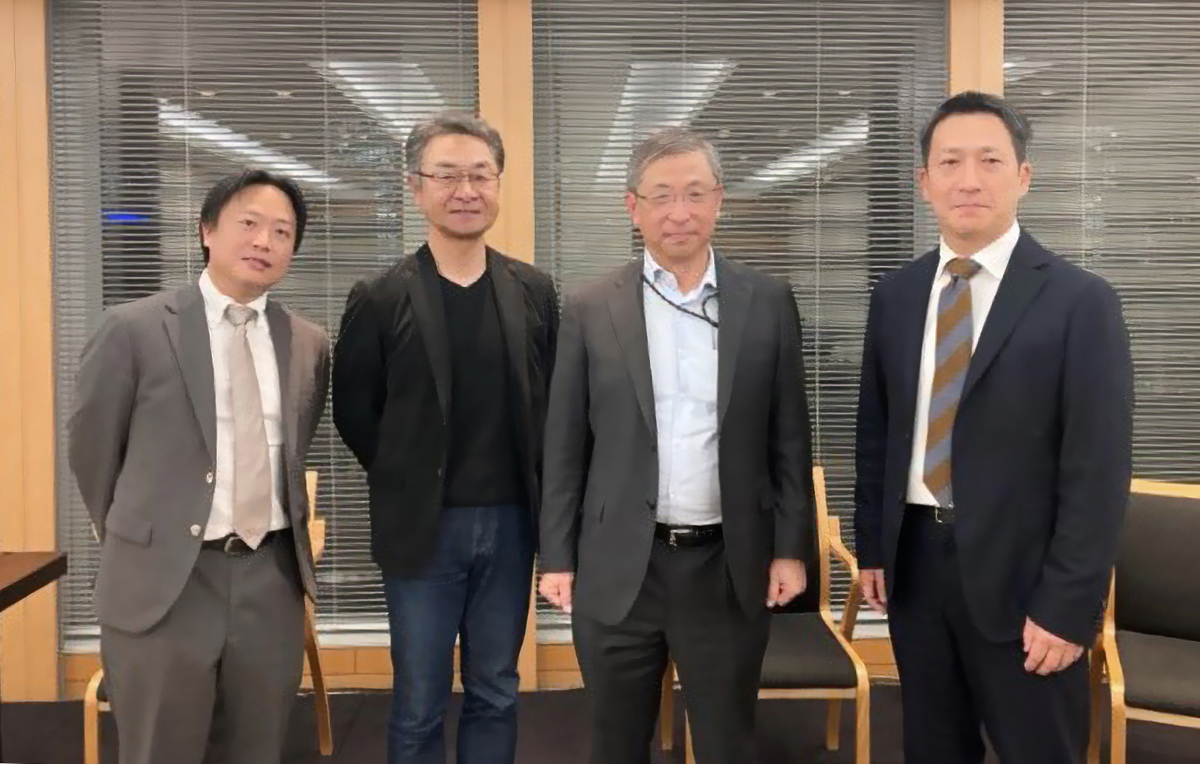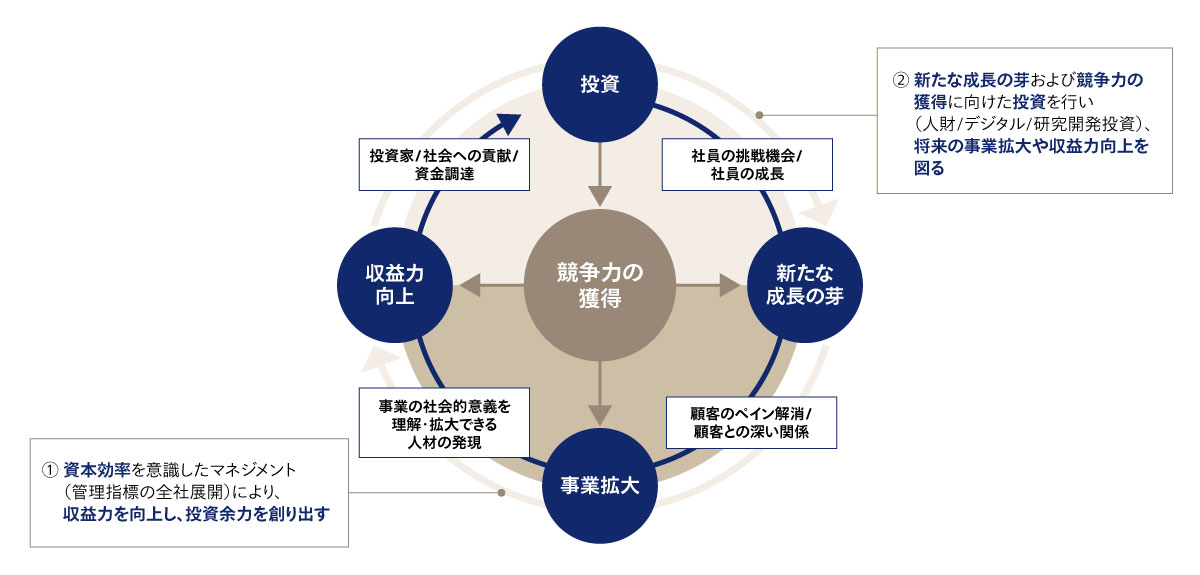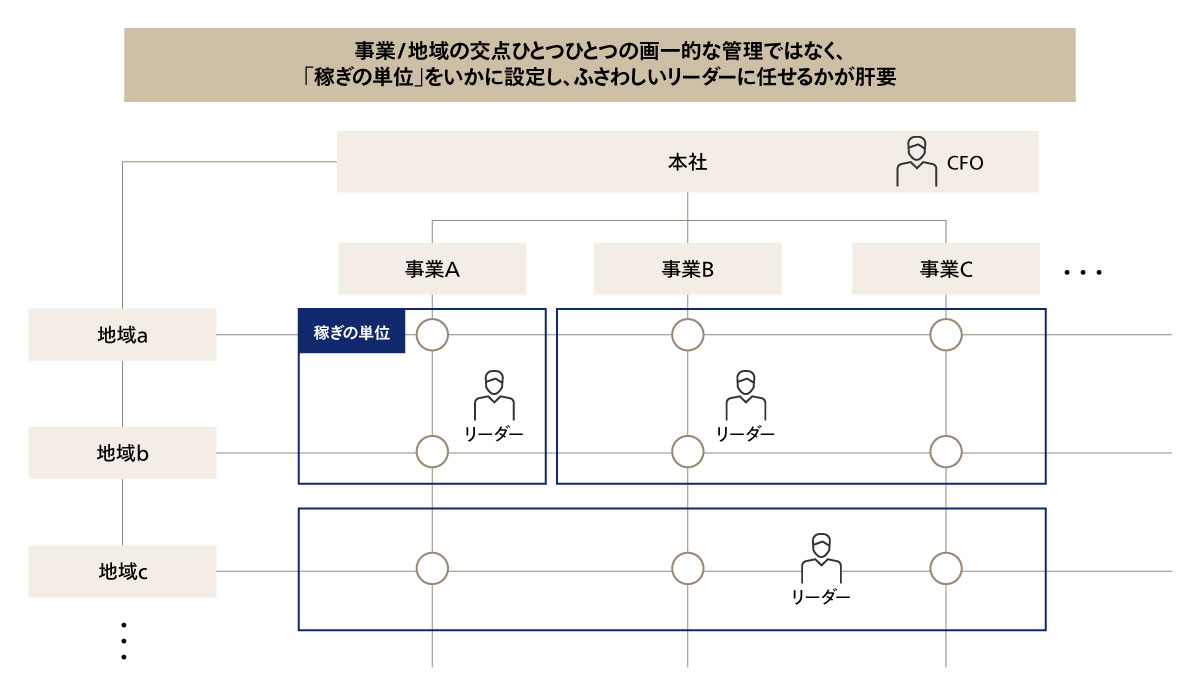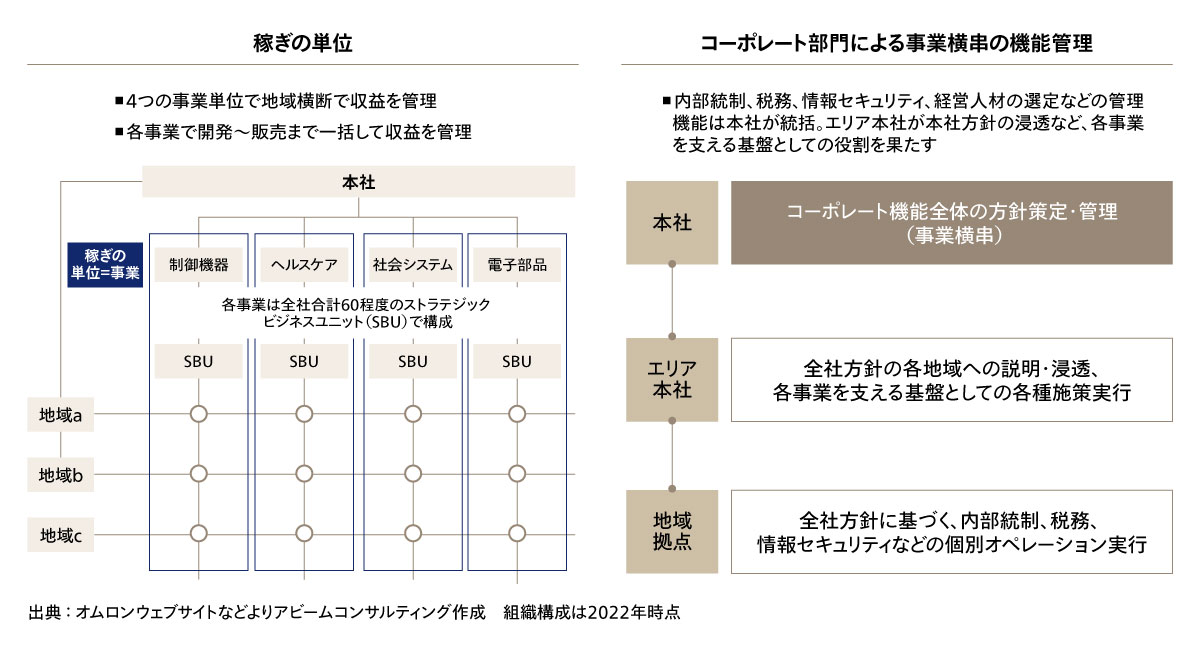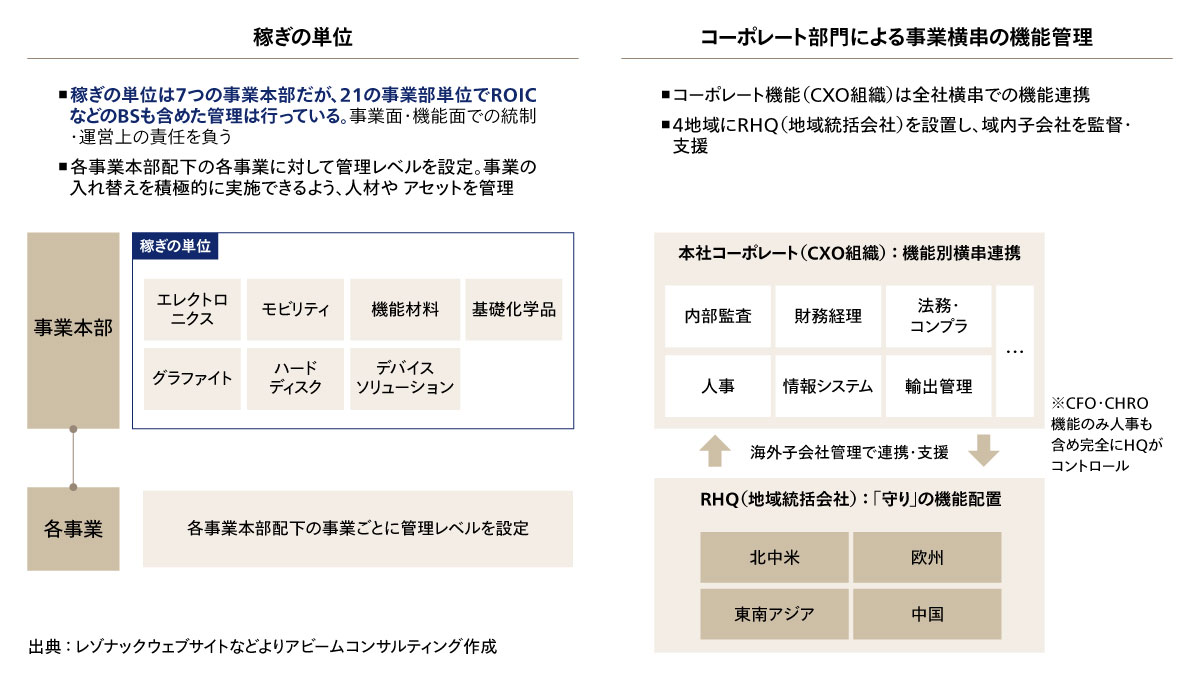競争優位の源泉に投資を振り向け、自律分散化した経営ができるようにするためには、戦略・文化のアラインメントが重要となる。オムロン、レゾナックにおいて、戦略・文化のアラインメントを取るためにどういった取り組みをしているのか。
「オムロンの根本は企業理念経営です。採用・育成・配置を行う際も、企業理念に重きを置き、経営幹部には企業理念に対する深い理解・共感を求めます。また、企業全体だけでなく、事業によってどうより良い社会を作るか、社会における事業の価値・存在意義や当社の競争力を事業のリーダーと共に議論しています。企業理念を浸透・実現することで、グローバルにおいても、理念に共感しオムロンにコミットする人が自然と集まってくる、そこに地域差はあまりないと感じています。」と日戸氏。
「レゾナックでは、昭和電工と旧日立化成の統合にあたり、高橋秀仁社長を中心とした新たな経営チーム“チーム高橋”を発足しました。チーム合宿を実施するなどしてチーム内での心理的安全性を高めることで、反対意見も含め意見を自由に言い合える経営チームを築きました。経営理念および戦略の再構築に向けて侃侃諤諤の議論を重ねた結果、半導体事業への大胆な投資を行うべきという結論に至りました。半導体以外の部門長から『自部門の投資を抑えてでも半導体に投資すべき』という意見も出るようになり、部門長がレゾナック全体の企業価値向上に向けた各部門の役割を認識できるようになってきています。」と染宮氏。また、別々の会社が統合し、社内でも様々な意見がある中で、グローバル本社の経営陣が意見を自由に言い合える関係を築き、一枚岩になることが重要であると語った。
マーサージャパンの山内氏からは、戦略・文化のアラインメントをとるために人材・組織面でどういった工夫をしたか、と両名に質問を投げかけた。
まず、日戸氏は「従業員にとっては結局のところ、自分がどう評価・処遇されるか、というのが大きな関心事です。事業ごとに評価・報酬制度があまりに異なると不公平感が生じるため、グローバル共通の評価ポリシーと評価テーブルを策定し、競争力を持った評価・報酬制度の構築に努めました。また、経営層における組織運営の観点では、全社方針について侃侃諤諤議論した上で、ただし一度合意に至ったからには、きっちりと方針に従い、実行することを求めました。」と話す。
次にレゾナックでは、「評価・報酬制度を一から構築するにあたって、階層を減らし、ジョブディスクリプションを明確にすることで、階層の整合性が横断的に取れるよう根本から見直しました。また、文化の観点では、社長自らが事業所や子会社を訪問し、年間約70回タウンホールミーティングやラウンドテーブルを開催しています。現場と双方向のコミュニケーションを取り、社長に意見しても良いという心理的安全性を構築し、文化の変革に挑んでいます。」と染宮氏。
オムロン、レゾナックともに、戦略・文化をアラインメントするために、経営理念の浸透、経営チームの連携強化に加え、制度設計のアップデート、組織風土の改革など、あらゆる角度からの工夫を行っていた。また、取り組み自体が目的化することなく、目指す姿を明確化した上で両社の実態に即した取り組みがなされていることが伺えた。