キャリア採用
障がい者採用
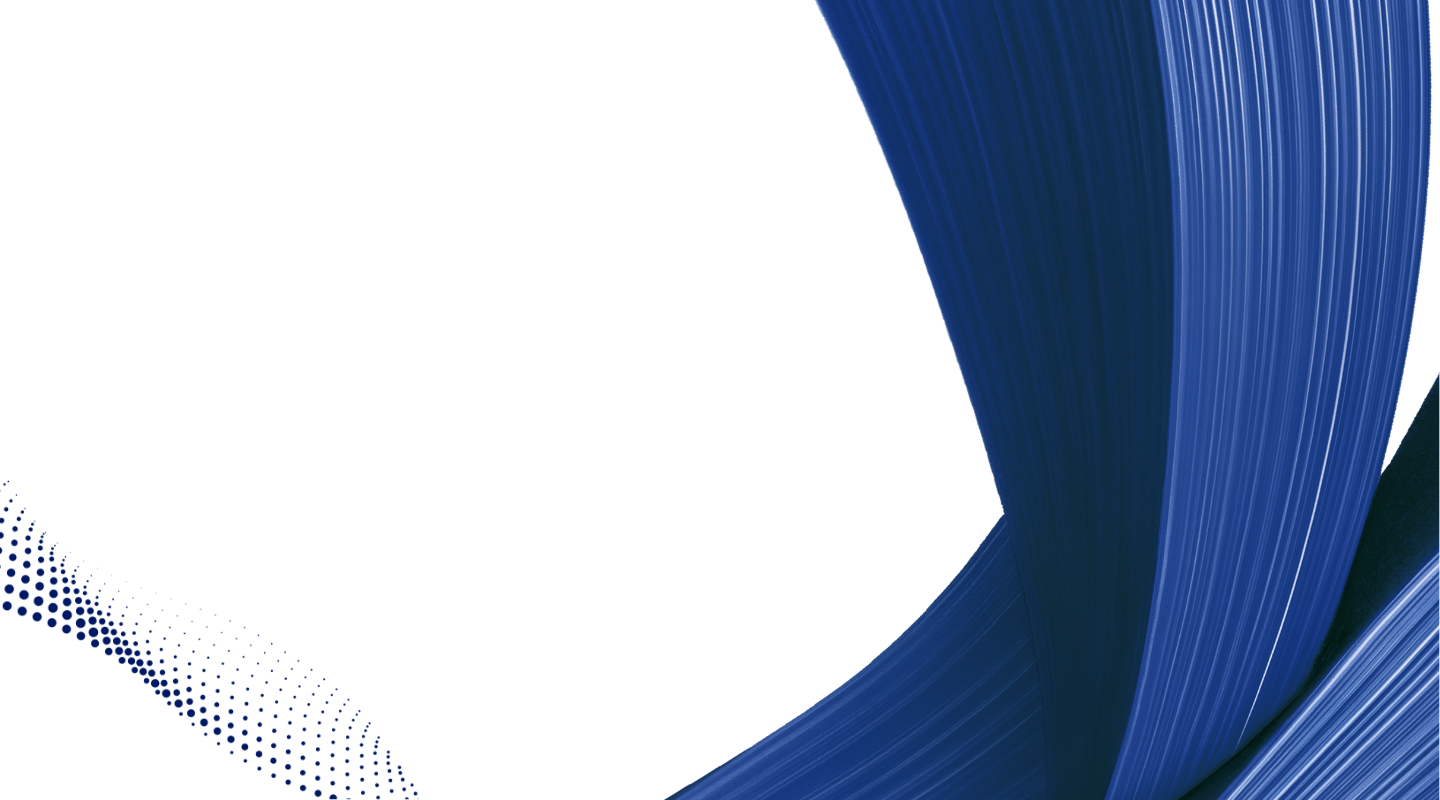

少子高齢化、防災・インフラ老朽化、地方都市の縮小など、日本全国で社会課題は複雑化の一途をたどる。こうした課題の解決には専門的な知見と実行力が不可欠だが、アビームコンサルティングの公共ビジネスユニットは、20年前の部門立ち上げ以来、公的機関に伴走するパートナーとして歩んできた。ユニット長の松田智幸が「中長期的な社会課題の解決」と「公共性と経済性の両立」に取り組む部門の使命と意義を語る。
上席執行役員 プリンシパル
公共ビジネスユニット長
松田 智幸
大学卒業後、外資系コンピューターメーカー、外資系コンサルティングファームを経て、2003年アビームコンサルティングに入社。官公庁、地方自治体、文教・研究、医療・健康・福祉、社会インフラ分野を中心に、多数の経営改革・業務改革・調査研究等のプロジェクトを統括。また、社外取締役、自治体の特命大使、大学との共同研究事業への参画、執筆、講演等、活動は多岐に渡る。
資格)システム監査技術者試験合格(IPA認定)、プロジェクトマネージャー試験合格(IPA認定)、中小企業診断士試験合格、防災士合格 等
著書)公的組織の経営改善ハンドブック(編著、中央経済社)、バランススコアカードによる学校マネジメント(共著、明治図書)、自治体業務改革とシステム調達(寄稿、日経BPガバメントテクノロジー)
公共ビジネスユニット(以下、公共BU)の仕事を一言で表現するならば、「社会課題の解決を国の中枢から地方まで変革を支援する部門」です。
官公庁、地方自治体、文教、医療など、私たちが向き合う公共領域のクライアントは多岐にわたります。それぞれで抱える課題も、目指す理想も異なりますが、共通しているのは、「日本の社会をより良く変えていきたい」という強い想いを持っていることです。
変革を実現するのはあくまでクライアントです。私たちはコンサルタントとしての専門性を活かし、日本の未来を見据えた政策づくりから、目の前の社会課題の解決まで、一貫して支援することを使命としています。そして、私たちが重視しているのは、「最初に相談すべき相手」として信頼される存在であることです。クライアントが取り組もうとしている政策や業務改革を推進する際に、まずは最初にご相談をいただき、意見交換ができる間柄であり続けることを目指しています。そのためには、単なる計画書等の作成=アウトプットにとどまらず、その先の成果=アウトカムまで見据えて支援することが必要不可欠です。

例えば、「事業計画の作成を依頼された」とします。事業計画は成果物(アウトプット)ですが、成果(アウトカム)につながらなければ、ただの紙です。公共BUは常に成果を追求する組織であり、私たちは、成果にこだわってきたことが、現在のクライアントとの信頼関係につながっていると感じています。何よりもこの「アウトカム志向」がアウトプットの質そのものを変えるのです。戦略や計画は、訓練すれば作れるようになります。しかし、本当に効果につながるかどうか、実行可能かを考えると、難易度は格段に上がります。私たちはアウトカムを出すために「使えるアウトプット」を作ることを、強く意識して仕事に臨んでいます。
20年前、私は公共BUを立ち上げました。当時は実績も信頼もない、まさにゼロからのスタートでした。地方に行けば「東京のあなたに何が分かる」と一蹴され、別の地域でも同様に簡単には受け入れてもらえませんでした。それでも諦めずに足を運び続け、小さな案件から一つずつ実績を積み重ねてきました。
一つひとつ愚直に成果を積み重ねてきた結果、今ではマネージャー以上の多くのメンバーが、政府の委員会のメンバーとして委嘱されたり、自治体のアドバイザーを務めたりしています。こうした取り組みを通じて、国や地方の政策決定にも直接関わるようになりました。また、全国の自治体から信頼を寄せられ、真っ先に声をかけていただける存在へと成長しました。かつて「何が分かるんだ」と言われた私たちが、今では「まず相談したい相手」として選ばれるようになりました。
公共BUでは、さまざまな社会課題に取り組んでいますが、なかでも特に緊急性が高いテーマが「地方創生」と「防災・インフラ対策」です。
地方創生については、衰退を食い止めるだけでなく、経済成長を目指すアプローチが必要です。行政現場では、少子高齢化に伴う職員数の減少と、住民サービスの維持・向上の両立という課題に直面しており、外部の専門知見を活用する必要性が高まっています。
防災・インフラ対策については、連日ニュースで取り上げられているように、災害の激甚化が進み、対策を講じてもなお新たな課題が生まれる「終わりのない対応」が求められている状況です。被害の規模も大きくなっている中で、本来であれば、事前の投資やプランニングに力を入れるべきですが、日々の防災業務で手一杯という現状。迅速な情報収集体制の構築、早期警戒情報の発信、住民への避難指示など、すべてが行政サービスとして求められています。

危機的状況の中、継続的支援は必要不可欠であり、私たちのようなコンサルタントが真価を発揮できる分野だと捉えています。私たちの強みは、全国規模でクライアントを支援してきた実績があることと、それらを「面」として捉えてナレッジを蓄積していることです。例えば、東京で得た医療分野の事例や知見を神奈川でも大阪でも活用することで、専門性や知識のレベルも深化していきます。
自治体ごとの支援を一つひとつ丁寧に積み重ねてきた結果として、私たちは全国規模の動きを俯瞰的に捉えられる立場にあると自負しています。クライアントから求められることは、ベンチマークとベストプラクティスの提供です。全国の事例を知り尽くしているからこそ、「他の自治体ではすでに廃止している」「新しい手法が効果を上げている」「これは制度的にやらなくてもいい」といった具体的な比較検討の材料を提示できます。そういった実際的なアドバイスができるのは、全国の事例を知り尽くしているからこそだと自負しています。
私はこういった活動を「深化と進化」と呼んでいます。深化の方は前述の通りですが、進化の方は、時代に合わせた解決手法の革新を指します。課題そのものはなくなりませんが、解決の仕方は刻々と変わっています。10年前にはなかったDXという言葉は今では主力の手法の一つです。「深化と進化」の両輪をひたすら回し続けることで、組織も人材も成長し続けられますし、公共BUとしてもそういった仕組みづくりに努めています。
また、メンバーにはあまり数値目標を意識させないようにしています。もちろん、数字を追いかけることは事業運営において重要です。ただ、売上などの数値的な責任と権限は事業部長である私が担うべきだと考えており、それ以上に大切なのは、数字の先にある社会課題やクライアントのニーズを正しく捉えることです。
そのため、組織として常に国の動きや地方の実情を分析し、「今年・中長期的にはこれをやるべきだ」とメンバーと共有・協議しています。社会やクライアントが今、真に求めている取り組みに集中して取り組んでほしいと願っています。
クライアントを第一に考え、そのアウトカムを志向して仕事に向き合っていれば、結果として自然に成果はついてくる——私はそう信じています。

組織運営において私が最も重視しているのは、メンバー一人ひとりが「高い志」を持って仕事に取り組むことです。私はよく、「夢は自分のためのもの、志は誰かのためのもの」とメンバーに伝えています。
というのも、コンサルタントはクライアントや社会のために知見を提供する仕事だからです。だからこそ、「誰かのために働く」という意識を持ち、高い目的意識を持って仕事に取り組んでほしいと考えています。
もう一つ大切にしていることが「進化」です。先ほどお話しした深化と進化の考え方を、組織的にも個人レベルでも止めない。組織も進化するから、メンバーにも成長し続けてほしいという思いを込めています。その進化を支えるために、資格取得への積極的な支援に取り組んでいます。私たち公共BUは、社内でも特に資格取得への意欲が高い部門です。組織の上位層や私自身もその姿勢を体現するため、自己研鑽と資格取得は継続しています。
私自身が率先して学び、資格を取得することで、言葉だけでなく行動でもメンバーに示し、説得力を持たせたいと考えています。リーダーは体現者であるべきだと常々考えています。こういった姿勢が組織全体に浸透した結果として、メンバーも自発的に学び続ける文化が根付いているのではないかと思います。
もちろん強制ではありませんが、公共セクターの仕事では学術的な裏付けも必要ですし、資格を取得しているということは、一人のコンサルタントとしても、自信やクライアントへの信頼につながる要素です。
このように「高い志」を持って学び続けたいという価値観を共有できる人材を採用し、育成してきた結果、現在の公共BUの形ができあがったと思っています。スキルは入社後にいくらでも身につけられますが、価値観は一朝一夕には変えられません。だからこそ、同様の価値観を持つ方との出会いを最も大切にしています。
公共BUの採用は競争が激しく、高い志を持つ方々をお迎えしています。確かに 狭き門ではありますが、その分、やりがいの大きい仕事に取り組める環境があります。まだまだ支援が十分に届いていない地域や課題が多く残る中で、私たちがゼロから築き上げた組織を一緒に成長させ、日本の未来を共に創っていける仲間と出会えることを心から楽しみにしています。