キャリア採用
障がい者採用
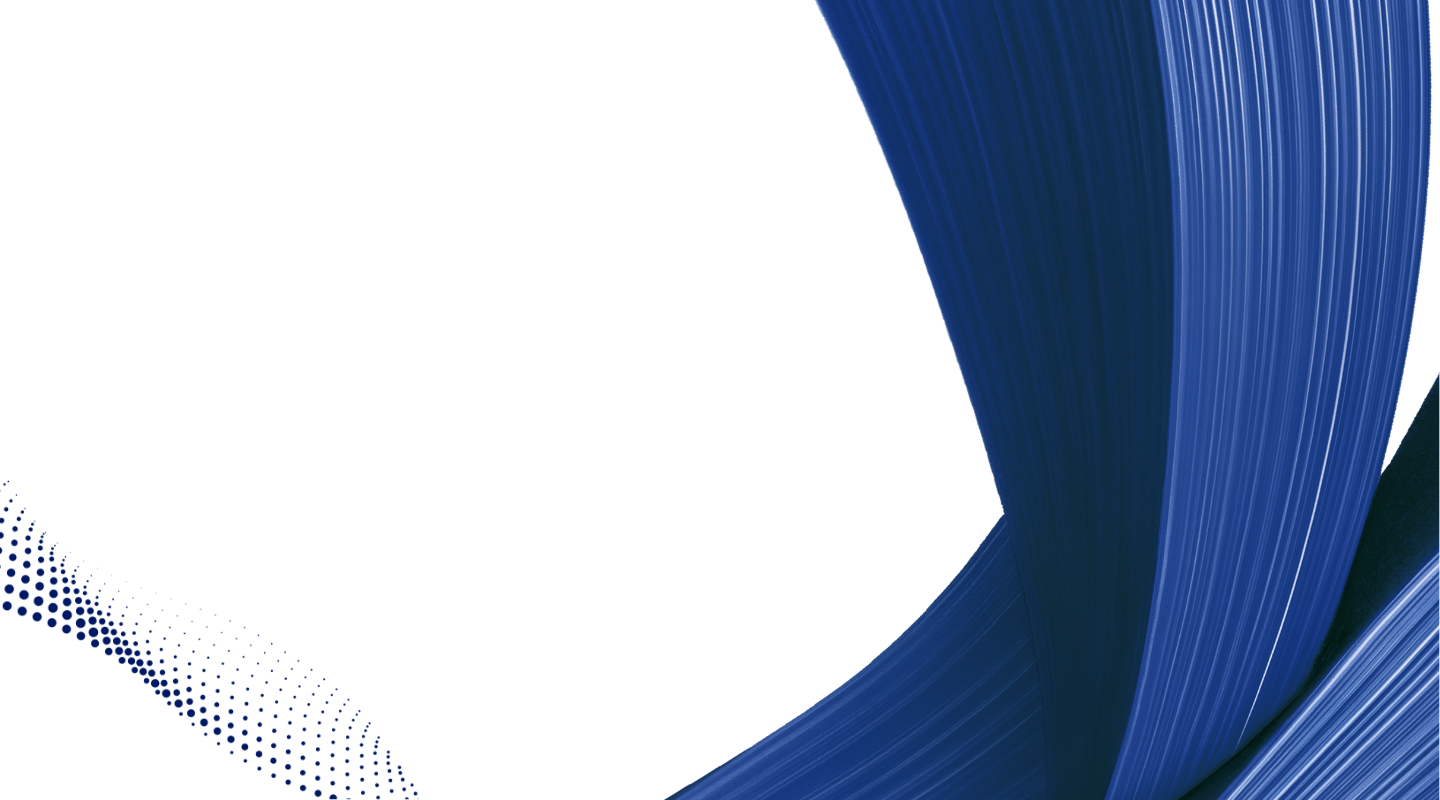

「日本人の労働生産性を世界水準にする」——明確なミッションを掲げ、発足後から成長を続けるアビームコンサルティングの「人的資本経営戦略ユニット」。既存の「人事」という枠を超えて企業と個人の最適なマッチングを追求し、コンサルティング会社の“当たり前”にとらわれない本質的な価値提供を追求する。久保田勇輝ユニット長に、設立の背景と日本企業変革への想いを聞いた。
執行役員 プリンシパル
人的資本経営 戦略ユニット長
久保田 勇輝
新卒で外資系のコンサルティング会社に入社し、人事コンサルティングに7年間従事。その後、PR系のベンチャー企業で新サービス開発などを手がけ、ソフトウェアベンダーに転職したのち、部門立て直しのために、コンサルティング会社に復帰。HRテクノロジー領域におけるリーダーと人事のストラテジーとプロセス改革のコンサルティングのリーダーを兼任。2022年に人的資本経営領域を立ち上げるために、アビームコンサルティングへ入社。
人的資本経営戦略ユニット(以下、人的資本経営SU)が生まれたきっかけは、コンサルタントとして経験を積んだ40歳を過ぎた頃のことです。同世代のコンサルタントと「自分が人生で関われるプロジェクトは残りいくつかあるか」という話になり、「10プロジェクトあるかないかではないか」という結論に至りました。そこで、私が強く想ったことは「残りのコンサルタント人生では、社会的意義のある仕事に振り切って、日本が本当の意味で元気になれる仕事に挑戦したい」という想いでした。
これまでの経験やスキルを活かしてコンサルタントだからこその価値を創出するとしたら何か。そう考えた時に浮かんできたのが、日本の労働生産性の低さという構造的課題の解決でした。

2023年のデータで日本の時間当たり労働生産性は、OECD加盟38カ国中29位という状況です。時間当たり労働生産性とは一人当たりのGDPを労働時間で割った値で、この数字が低いということは、同じ時間だけ働いても他国と比べて生み出される価値が少ない。つまり、日本の生活水準が相対的に下がり続けることを意味します。この課題解決に取り組むことが、真の社会貢献になるのではないか。
そんな想いを持って、アビームコンサルティング(以下、アビーム)の当時社長だった鴨居達哉や、現社長の山田貴博にビジネスプランを説明したところ、「その考え方は“人的資本経営”そのものではないのか? 我々としても人的資本経営というテーマを今後の重点投資領域としていきたいことからも、ぜひアビームで新たなチャレンジをしてほしい」と言われました。その言葉で「人的資本経営」という領域で、これまで培ってきたすべての経験や知見をアビーム注ぎ込むと心に決めました。
そこから、自分がやるべきだと信じたことを「人的資本経営」という考え方に重ね合わせて、私たちなりのサービスを作り上げてきました。
私たちがやりたいことは、表面的な人事制度の変更ではありません。人事の領域はバズワード先行型になりがちで、ジョブ型、成果報酬、最近では生成AI……こうした言葉が先行するがゆえ、「目的のないハウツー」が横行しているのが現状だと思っています。
私が重視しているのは、こういったバズワードに惑わされることのない、企業と従業員の最適なマッチングです。たとえば、これまで「年功序列」だった多くの日本企業が、「成果や貢献度に合わせた報酬を」という方針に転換している。でも、成果や貢献度は従業員だけの責任ではありません。会社が従業員にどんな機会を提供しているかにも左右される。
つまり、一方的に何かを要求するのではなく、お互いがマッチングを図る時代になったということです。会社が「実現したいこと」を伝えると同時に、「従業員にどんな機会を提供できるのか」についても示す。従業員も同じように「自分自身はこういったことが会社に価値提供できるし、こんな機会を求めている」と、お互いが伝え合い、理解し合える状況を作る必要があります。
このマッチングで重要なのは、スキルだけではありません。どのような時にモチベーションが上がるのか、どのような働き方がしたいのか、どんなコミュニケーションが心地いいのかなど、価値観を含めた多角的な視点でのマッチングが生産性向上には不可欠です。先ほどバズワードにも挙げましたが、生成AIの普及によって、このマッチングがより重要なっていると考えています。
生成AIで代替されるような仕事に就いている人は、いずれ労働市場における価値を失うのではないかという話は、皆さんも聞いたことがあると思います。しかし、その未来を見据えて、その人たちに「生成AIに代替されない仕事」や「生成AIがあるからこそ新たに必要とされる仕事」をできるようになってもらう。その人の市場価値を維持し、従業員が継続的に会社に貢献するためにも、適切なマッチングが重要です。
そのために重要なことは、日々刻々と変化する働くことを可視化、シミュレーションし、先回りして対策を考え、実行することです。その一環として、私たちは人材ポートフォリオや人材バランスシートを作成し、会社が求める人材の量と質が満たされているかどうかを定量的に把握できる仕組みを構築しました。
従来は「10億円を10人で稼いでいたら、100億円稼ぐためには100人が必要」という量の単純な倍数で判断してしまいがちでした。でも、実際にやってみるとうまくいかない。なぜかといえば、その集めた100人が「10億円を稼げる10人」と同等ではなかったからです。だからこそ人材ポートフォリオを作って、量だけでなく質的にも満たされていることを確認することが重要です。そうすることで、適切な人件費の配分を行うことができますし、100億円を稼ぐためには人材育成が必要だとも見えることで、経営陣として何をすべきかがわかるようになります。
企業と従業員の最適なマッチングを実現するためには、CHROだけでなく、こうしたデータを基にCEO、CFOも「人材を数値的に把握する」ことで共通言語を持ち経営判断を行っていくことが欠かせません。実際に、ある大手企業の役員約20人に対して人的資本経営の重要性をプレゼンする機会がありました。そのプレゼン後に役員の方から「これまで人事部門だけが考えていた課題が、実は経営の根幹に関わる戦略的テーマだった」という言葉をいただきました。
人的資本経営戦略ユニット独自の動きとしては、毎週月曜日を「研鑽デー」と称して、各人が必要な知識やスキルを磨くことに時間を割いています。多くの企業では社員向けに学習時間を設けようとしますが、自主性に任せてしまうと「忙しいから」という理由でうまくいかないケースが多いです。それであれば組織として「忙しさ」を言い訳にしないように、月曜日固定で学習時間を確保してしまおうと考えました。
研鑽デーでは、チームの戦略について議論したり、一人ひとりのキャリアについて話し合ったり、外部からゲストを招いてディスカッションしたりする場を設けています。過去には、アビーム内のAI専門チームから生成AIについて勉強会を開いてもらい、それをもとにチーム全体で語り合ったこともあります。他にも、私が尊敬する外部企業の経営者が書かれた本がチームで話題になった際には、クライアントのネットワークを通じて、その外部企業の方々を招いて、本の内容について詳しくお聞きする機会を設けました。

他にも、私たちはキックオフも半期に1回、毎回少しこだわって開催しています。たとえば、丸一日かけた「目標設定ミーティング」を行ったこともあります。オフィスや会議室にいると日常業務に気を取られてしまうため、いつもとは全く違う場所で集中して行いました。午前中は山登りでチームビルディングを図り、午後は山小屋でじっくりと各メンバーの目標設定を行う。自分自身が日々の仕事から離れて、目標やキャリアを考える時間を意識的に取ることが、最大の投資だと思ったからです。
チームとしてもメンバーそれぞれの生産性を高め、単なる休日を増やすのではなく、個人の充実と組織の生産性向上を両立させる働き方を目指しています。

今、まさに人的資本経営は経営課題として認識されるようになってきています。最初は懐疑的だった企業も、「うちの会社を人的資本経営という文脈で変えてほしい」と求められることも少なくありません。
人事や人材領域というのは、売上に対する直接的な貢献を測りにくい分野です。しかし、私たちが取り組んでいるのは、同じ時間でより多くの価値を生み出す、つまりは生産性を向上させる仕組みづくりに他なりません。営業部門が売上という分子を大きくする役割だとすれば、私たちは労働時間という分母を最適化することで、結果的に労働生産性の向上に貢献できるのではないかと考えています。
人的資本経営戦略ユニットで働く魅力という点では、人事という枠にとらわれず、「人にまつわる課題解決」という観点から、CxOをはじめとして人事部門以外の部門も巻き込みプロジェクトに携わることができ、経営・事業・従業員といった多面的な観点を持った成長ができます。また、日本発グローバルという形で、クライアントのグローバル化に伴う人的課題解決や自組織自体グローバル展開に携わることができる点も大きな魅力です。
私自身の考えとして、テンプレート化していないコンサルティングに取り組めば取り組むほど、成長スピードは速くなります。なぜなら、考える時間が多くなるからです。労働時間に依存しない成長スピードの速さ。これが私たちのチームで得られる価値の一つだと思います。
人に向き合う仕事は難しいけれど、面白い。そして、社会へのインパクトも大きい。データとしても変化が見えますし、目の前で人が変わっていく姿も見られます。日本企業の本質的な変革に携わりたいという想いを持つ方々と、一緒に取り組んでいきたいと考えています。