キャリア採用
障がい者採用
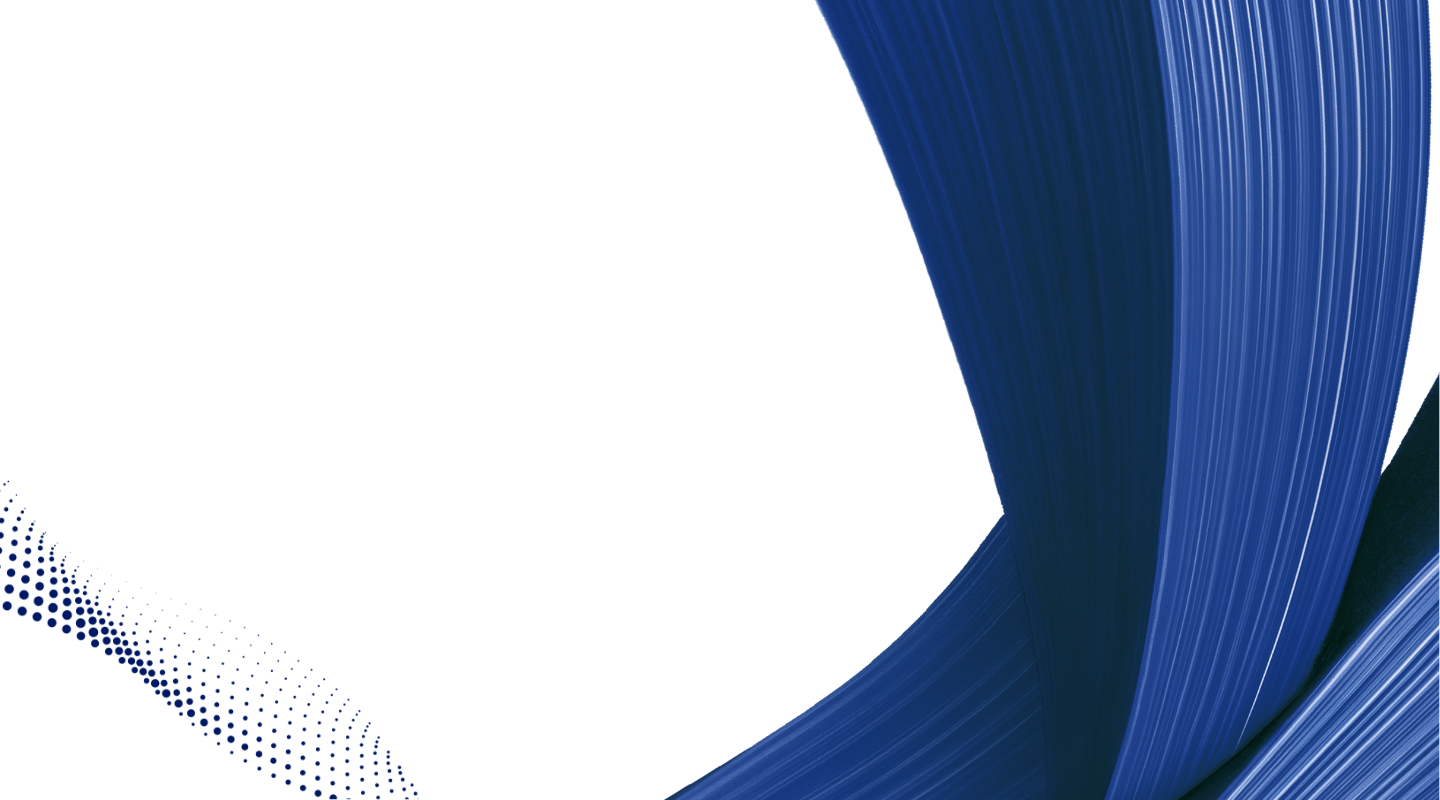

ソフトウェアディファインドによる製品設計の高度化、EV化の進展による競争構造の変化、サステナビリティへの対応など、製造業を取り巻く環境は激変している。戦略コンサルティング事業 製造ビジネスユニットは、自動車・モビリティ、電機・機械、素材・化学、石油・プラントエンジニアリングの4つのサブインダストリーグループを構成し、製造業全体の変革を支援している。舵取りを担う四十谷裕之ビジネスユニット長に、業界の構造的変化と向き合い方、そして「次を見据えることができるコンサルタント」チームであり続けるための製造ビジネスユニット特有の取り組みについて聞いた。
上席執行役員 プリンシパル
製造ビジネスユニット長
四十谷 裕之
大手物流会社を経て、2000年アビームコンサルティングへ入社。2005年より、中国(上海)、東南アジア(タイ、マレーシア)、US(ロサンゼルス)での海外プロジェクトを複数経験。2006年執行役員、2010年よりABeam Consulting Thailandのマネージングディレクターを5年間務める。2015年に帰任後、製造&コンシューマインダストリーのビジネスユニット責任者。現在は戦略コンサルティング事業の金融、商社・コンシューマーおよび製造のエンタープライズ領域の所管執行役員を担い、製造ビジネスユニット長を兼任する。
アビームコンサルティングの製造ビジネスユニット(以下、製造BU)では、欧米発のベストプラクティスを単純に当てはめるのではなく、日系企業ならではの文化や築いてきた強みを最大限に活かし、中長期的な経営視点を尊重しながら、最適な変革の道筋をクライアントと共に伴走するアプローチを大切にしています。
製造業は「モノからコト」への大きな転換期を迎えました。従来の「モノを売って終わり」というビジネスから、「コト売り」と言われるように、製品を販売するだけではなく、継続的な関係性を維持する中で、顧客の体験価値を新たに創出・提供していくビジネスへと変革が進んでいます。例えば、自動車OEMでは、販売した車両から取得できるデータを活用しながら、移動ニーズに応じたLTV(Life Time Value)の提供など、業界の垣根を超えた社会貢献のトレンドが見られます。

私たちはこの変革において、バリューチェーンの中でも特に重要とされる「上流と下流」に注力しています。設計開発などの上流部分では、顧客ニーズの把握や競合との差別化がカギになります。販売後のサービスの下流部分では、顧客体験(CX)の向上への収益構造の転換が重要なポイントとなっています。
ソフトウェアが鍵を握る設計開発領域と、単なる製品を超えたCX──この両端での価値創造こそが、自動車OEMのみならず日系製造業における競争優位性の源泉だと考えています。
製造BUが注力する4つの分野では、それぞれ異なる変革の波が押し寄せています。
自動車・モビリティ分野では、ハードウェア中心のものづくりからソフトウェアディファインドへの転換が急速に進んでいます。数年前にはCASEやMaaS(Mobility as a Service)という概念が登場し、自動運転やコネクテッド技術、移動を通じたコミュニティへの注目が高まりました。その後、新興国(特に中国)のEVメーカーが台頭し、価格競争力に加えて電気自動車に対する技術的対応の違いが、従来の競争環境を大きく変えました。
先ほどお話したように、日系自動車OEM各社はデータ活用やサービス提供を積極的に進めています。例えば、顧客がレストランに向かう際の最適なルート提案、駐車場の空き状況案内、さらにはレストランでの体験向上まで含めた総合的なモビリティサービスの提供は、まさに「モノからコト」への典型例といえます。
電機・機械分野でも同様の変化が見られます。製造設備や産業機械では、組み込み型半導体やソフトウェアが核となり、従来の機械的制御から、高度かつインテリジェントな運用が実現されています。半導体市場では、自動車用、組み込み型、データセンターなど用途別に需要の変動があり、各企業はこの変化に柔軟に対応しなくてはなりません。
素材・化学分野では、既存事業の効率化と新素材開発による新規事業開発が大きな経営アジェンダと捉えています。歴史ある企業が多いこの業界では、従来の強みを活かしつつ、プラスアルファの「新たな勝ち筋」が欠かせません。例えば、繊維メーカーが航空機材料向けの炭素素材の開発を手がけたり、CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)といった事業成長を見据えた設備投資の強化を図るなど、応用領域への展開が活発化しています。既存事業の最適化だけでなく、技術革新による新規事業も同時に求められています。
石油・プラントエンジニアリング分野では、業界再編や統合が進む中、上流から下流までの幅広い事業領域における効率化が経営課題となっています。従来の事業基盤を維持しながら、クリーン電力を始めとする新たなエネルギーソリューションへの対応も模索されています。水素など次世代エネルギーの検討も含め、モビリティ事業への参入など、中・長期的な視点での事業変革が求められます。
これら製造業界に共通する構造的課題は、過去の成功体験だけでは生き残りが困難になっており、新たな価値創造への事業転換が急務となっていると考えます。
昨今、特に注目すべきモビリティと素材技術へのトレンドは、EV化の次のステージとして浮上している環境・サステナビリティへの課題です。EVバッテリーのリサイクル、サーキュラーエコノミー、環境を意識したRe-Manufacturingへの対応などが新たな経営アジェンダとなり、総合商社も含めてビジネス機会として注目しています。製造BUは「次を見据えることができるコンサルタント」として、将来を見据えた新たな課題にもいち早く目を向け、クライアントと共にその社会課題解決に取り組んでいくことが求められています。
製造BUの大きな特徴は、多様なバックグラウンドを持つ人材からなるチーム構成にあります。海外ビジネスの経験者、ソリューションビジネスに精通した人材、特定事業や戦略コンサルティングの専門家などが在籍しており、現在ではメンバーの約半数がキャリア採用による人材で構成されています。こうした「新しい風」の流入により、従来の成功体験にとらわれない柔軟な発想や行動が促進され、組織全体の強化につながっています。この多様性を活かし、製造BUでは従来のSAP導入に強みを持つソリューション提供から、会社として掲げる「価値創出サイクル」への転換を進めています。
製造BUは、このサイクルの起点となる戦略構想フェーズを主に担い、クライアント経営層との信頼関係を築きながら、より高い付加価値の提供へと繋げていくのが大きなミッションと位置付けられています。

また我々は、自動車、電機・機械、素材・化学、石油・プラントエンジニアリングの4つの注力領域を設けていますが、領域横断的なプロジェクトの推進が大きな特徴です。モビリティ業界の新規事業検討に、石油業界出身のメンバーや素材化学技術を有するメンバーが参画するなど、業界の既成概念を破壊するような新たな発想を生み出そうと考えています。
さらに、金融ビジネスユニットや商社・コンシューマービジネスユニットなど、他部門との連携も積極的に行っており、業界や領域を超えた視点を持つことが、我々の重要な価値と位置づけています。
このような環境の中で、若手メンバーも特定の領域にとらわれることなく、幅広い知見を身につけながら、柔軟に力を発揮することが可能であることを期待しています。
このような事業・業界横断の取り組みの中、クライアントとのWin-Winの関係性をより発展させるために、共同事業としての「事業共創」も柔軟に取り組むことができることが、アビームコンサルティングの大きな強みだと考えています。

私たちが大切にしているのは、単なる課題解決にとどまらず、「次を見据えることができるコンサルタント」として新たな価値を提供することだとお話しました。この視点をチームとしても重視しており、毎年年初に「業界の変革テーマ」を自ら設定し、クライアントへ提言する活動を行っています。
年末から翌年の3月にかけて、メンバー間で喧々諤々と議論を交わし、今年度の注力テーマを練り上げ、4月にクライアントに向けて発信しています。これは、受け身の課題解決ではなく、私たち自身が変革の起点となって、クライアントに新しい視点を提供していくという製造BUならではの特色です。
私自身、物流の事業会社からコンサルティング業界に転身し、製造業の劇的な変化を目の当たりにしてきました。例えば、5年間のタイ駐在では、日本では当然とされる品質管理や納期管理の考え方が全く通用せず、現地文化に合わせた合意形成の重要性を痛感しました。異文化な中で学んだプロジェクトマネジメント経験は、今でも私の大きな財産になっています。
こうした実体験があるからこそ、クライアントとの議論でも、単なる机上の理論ではなく、現場での実践に基づいた提案ができると考えています。海外展開を検討するクライアントに対して、「現地ではこういうことが起きます」「こういった対処法があります」と具体的にアドバイスできます。実体験に基づく知見と書籍やレポートなどの理論的な情報と組み合わせることで、より現実的かつ実行可能な提案へとつなげることができます。
私たちが求めているのは、自分の専門領域にこだわりすぎず、柔軟に視野を広げられる方です。ある業界の経験者として採用されても、専門性や経験だけに留まらず、さらに領域を広げていただきたいと考えています。柔軟な考えを持った方にとっては、製造BUは成長の機会に満ちた環境だと確信しています。
これまでの成功体験に加え、新たな視点や柔軟性がより一層求められる時代に入っています。だからこそ、従来の延長線上ではない、新しいアイデアと行動力を持った方々と一緒に仕事がしたい。クライアントがまだ気づいていない課題を先取りし、一緒に解決策を考え、寄り添い、時には新しいビジネスまで創り上げる。そんな挑戦的な仕事に、ぜひ参加していただきたいと思います。