キャリア採用
障がい者採用
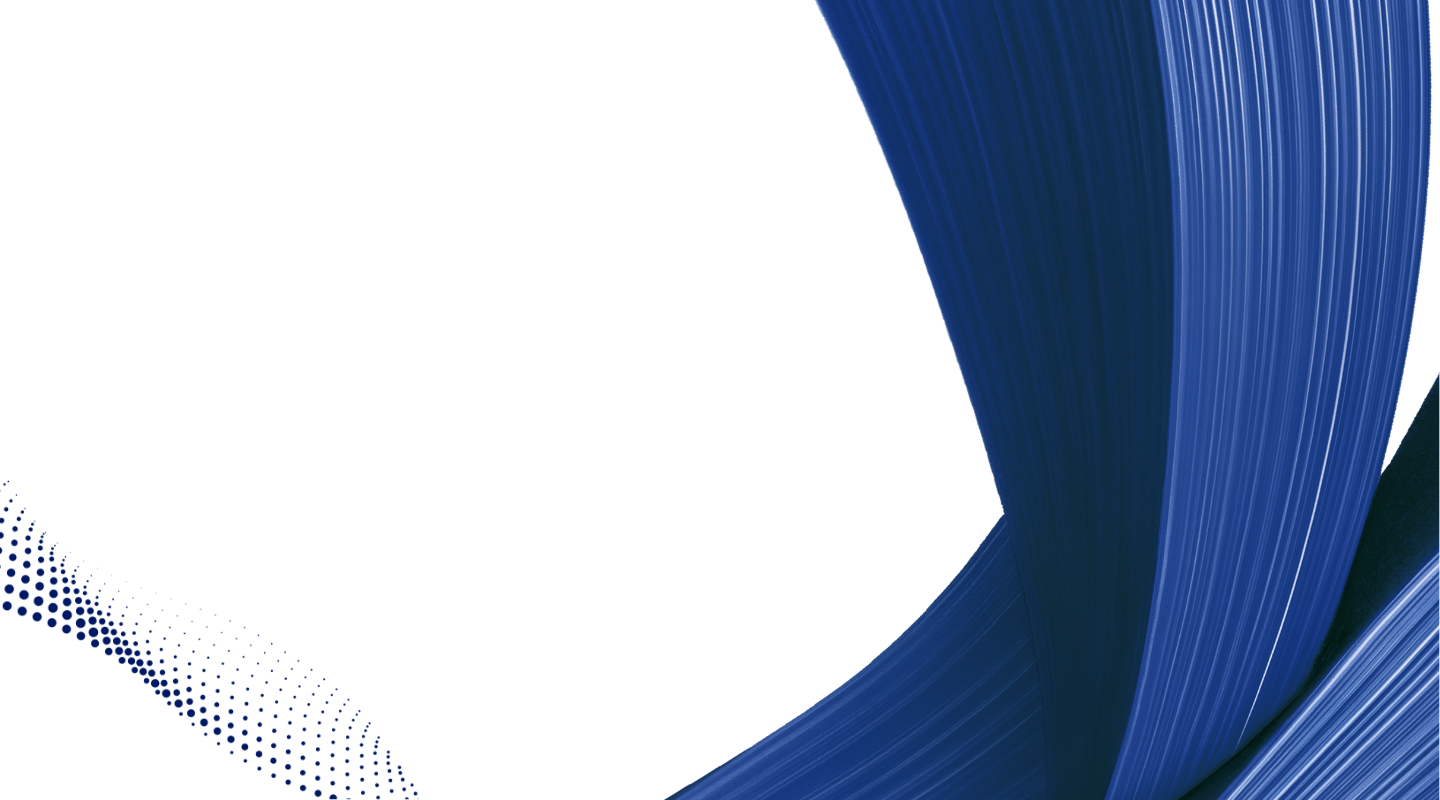

さらなる大きな変革期を迎えているインフラ業界。地政学的な不確実性や環境問題の高まり、デジタル化の進展などの環境変化の中で、インフラ事業者としての使命である「安定供給」への課題を常に抱えながらも、サステナビリティやグリーントランスフォーメーション(GX)といった新たな価値創造への対応も求められている。産業インフラビジネスユニットを率いる中村宏明ビジネスユニット長に、いくつものジレンマ・トリレンマを抱える業界・クライアントへの向き合い方を聞いた。
執行役員 プリンシパル
産業インフラビジネスユニット長
中村 宏明
大学卒業後、2001年4月にアビームコンサルティングへ入社。総合商社、エネルギー・鉄鋼系商社、電力・ガス大手を中心に、グローバル・グループ経営管理基盤整備、業務改革、経営・事業統合支援、DX・IT戦略など、幅広い分野のコンサルテーションに従事。現在は、エネルギーインフラを中心に交通、通信、都市機能なども含めた産業インフラ業界に対する戦略コンサルティングをリードしている。
産業インフラビジネスユニット(以下、産業インフラBU)は「電力・ガス」「トランスポーテーション(交通インフラ)」「不動産・建設」「通信・メディア」という4つのインフラ領域に対して横断的に戦略コンサルティングを提供しています。現在、約50名が所属しており、コンサルティング経験者とインフラ事業会社出身者が半々の構成になっています。
産業インフラ全体に共通する課題は明確です。それは「人口減少下でのインフラ維持・更新をどう実現するか」という点です。日本のインフラの多くは戦後から高度経済成長期にかけて整備されたものであり、老朽化が進行しています。かつてのように人口が増加していくトレンドであれば投資回収も予見できますが、人口減少トレンドの中でもいかにインフラを維持・発展させていけるのか。この課題は、通信、道路、鉄道など、すべてのインフラ領域に共通しています。

産業インフラBUの中でも、特に注力しているのがエネルギーインフラ分野です。理由は明確で、その背景には、他のインフラ分野が基本的に縮小傾向にある中で、電力は唯一需要が伸びる領域だからです。脱炭素化による電化シフトに加え、AI活用の拡大によってデータセンターの電力需要も急増していることから、まさに今、インフラ業界における成長の中心を担う分野となっています。
また、電力業界向けのコンサルティングが活況を呈している背景には「伸びる」「変わる」「人材不足」という3つの要因があります。需要が拡大すると共に、電力制度改革や脱炭素化といった事業環境の大きな変化も続いている中で、これらに対応する戦略人材が不足しています。そのため、コンサルティングへの期待値が高まっているわけです。
この10年間、アビームコンサルティング(以下、アビーム)は電力分野での実績を着実に積み上げ、主要なコンサルティングファームの一角を占めるポジションを確立してきました。大手インフラ事業者との実績・リレーションを基盤に、他ファームやインフラ事業者から新たに参画いただいたメンバーの知見を融合し、社内外の専門組織とも連携することで、幅広くより高度な支援を実現しています。現在も、多くのエネルギー事業者と先進的な取り組みを実施しています。
電力・エネルギー業界の最大の特徴は、その複雑な制約条件にあります。安全性(Safety)を前提にした、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environment)を全て検討する「3Eのトリレンマ」に加え、自由化による市場競争、地政学リスクからの安全保障など、複数の複雑かつ相反する要求が、同時に突きつけられる状況です。
「脱炭素化を推進しても停電は許されない」「市場は自由化されても料金値上げは許容されない」といった相反する要求を、同時に満たさなければならない。しかも、社会インフラを担う責任上、事業から容易に撤退することも許されません。しかし、このような困難な状況こそ、コンサルタントとしての知見と経験とコミットメントが最も活きる場面だと私たちは考えています。
産業インフラBUの価値は、メーカーのような発電技術や電力システム技術そのものの開発ではありません。時代の変化の中で変革を促す過程において、私たちの存在意義と貢献の機会があります。インフラ事業者は業界特有の事情から、視野が社内に閉じがちになる傾向があります。そこに対しても、私たちが時には第三者の専門家として、時には伴走者としてプロジェクトを推進することで、組織風土や従業員の意識改革にも貢献していきます。
「伸びる」「変わる」「人材不足」という3つの要因を挙げましたが、その中でも重視しているのは既存インフラや事業に対する「変わる」支援です。まさに既存のアセット・仕組みを見直し、再構築していく必要があり、インフラとしてはゼロから新しいものを作ることよりも難易度が高いため、コンサルタントにとって、大きなやりがいと成長機会がある領域だといえるでしょう。
たとえば、何もない広大な土地に新しい道路を建設するのと、既存の都市部で道路を地下化するのとでは、後者の方が圧倒的に複雑で、多くの調整が必要になります。同様に、新規で何かを作るより、既存の仕組みを変えることの方が困難であり、インフラの変革には、常に高度な課題解決力が求められます。
私たち産業インフラBUには、他社と差別化される3つの主要な強みがあります。
第一に、業界横断的な視点です。多くの競合他社は、「エネルギーと素材の組み合わせ」や「エネルギー単体」に特化しています。しかし、私たちは「電力・ガス」、「交通インフラ」、「不動産・建設」、「通信・メディア」といった幅広いインフラ領域を一つの組織でカバーしています。これにより、たとえば通信と電力の融合によるスマートシティ構想など、業界を横断した複合的なアプローチが可能となります。これが、他社にはない私たちの大きな優位性です。

第二に、異業種の知見を積極的に活用することです。私たちは、業界の専門家であること以上に、その業界に深く向き合い、変革実現までコミットする姿勢を重視しています。クライアント以上に業界動向を理解し、課題を整理し、解決策を提案します。この深い理解は、単なる経験や知識の積み重ねだけでは得られません。クライアント企業と同じ目線で業界課題に向き合い、変革の実現に本気で取り組む姿勢から生まれるものです。クライアント企業の業界を本気で良くしたい、変革を成功させたいという強いコミットメントから生まれる深い理解です。
変革の近道の一つは、先行する異業種の常識や先進事例を適切に導入することにあります。たとえば、電力自由化に伴う電力取引業務では、金融機関のトレーディングノウハウや総合商社のエネルギー取引の知見を応用し、戦略策定や体制・仕組みの構築を支援します。電力業界の変革には、電力以外の業界の先進的な取り組みを知っていることの方が、価値提供につながるケースも多いです。
三つ目の強みは、多様なチーム構成と柔軟な連携体制です。産業インフラBUは様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されているため、業界の固定観念に縛られずに、顧客の課題をフラットかつ客観的に捉えることができます。さらにアビームの強みの一つは、部門間の連携がスムーズであることです。たとえば、エネルギーのサプライチェーン最適化に関するプロジェクトでは、商社向けビジネス領域を担当する他のユニットとも密に連携し、領域を横断した包括的な支援を提供しています。

産業インフラBUが今後注力する重要テーマの一つが、「電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)」です。これは政府でも議論されており、データセンターの整備と、それに伴う電力・通信インフラの最適化が焦点となっています。
現在、データセンターは首都圏に集中しています。電力の長距離送電にはコストとロスが伴う一方で、通信の方が圧倒的に低コストで効率的にデータを送ることができます。そこで、再エネ適地である北海道や九州などの発電所近くにデータセンターを設置し、天候による発電量の変動に合わせてデータ処理の負荷を複数拠点間で動的に分散させる仕組みが実現し始めています。
このようなシステム全体の電力消費最適化は、電力、通信、クラウドサービスなど複数の専門知識を統合した新しいソリューションを提案できる私たちにとって、今後のビジネスの中核を担う可能性を秘めた、大きな成長領域だと考えています。単一の業界知識では解決できない、まさに業界横断型の課題解決が求められる領域だからです。
今後の事業成長を見据え、組織体制の強化にも注力しています。現在約50名のチームを、2030年までに100名規模へ拡大することを目指しています。同時に、他ユニットやビジネスパートナーとの連携によるレバレッジ効果を活かせ、実際のビジネス規模では300~400名相当のコンサルティングサービス提供を実現したいと考えています。
私たちが求めているのは、インフラという社会基盤へフォーカスを当て、その変革に本気で携わりたいという強い意志を持つ方です。非常に複雑な制約条件の中で苦心されている事業者の方々と共に、未来に向けて、一緒に良くしていきたいという想いを共有し、チーム一丸となって取り組んでいける仲間と出会えればと思っています。特にエネルギー関連を学んでいる学生の方々には、研究者や事業会社に加え、「コンサルタントとして社会の変革に携わる」という第三のキャリアパスがあることを、ぜひ知っていただきたいと考えています。
これはよくメンバーにも伝えていることですが、「大変な状況こそ、コンサルタントにとってのビジネスチャンスである」という考え方があります。
「大きく変わる」ときこそ色々な歪みが生まれ、世間一般で言う「大変」な状況であればあるほど、私たちの価値が発揮できるということです。産業インフラの領域はまさにそのような環境にあり、クライアントが困難な状況にある時こそ真に求められる仕事です。だからこそ、やりがいがあり、大きな価値を提供できるフィールドだと考えています。