キャリア採用
障がい者採用
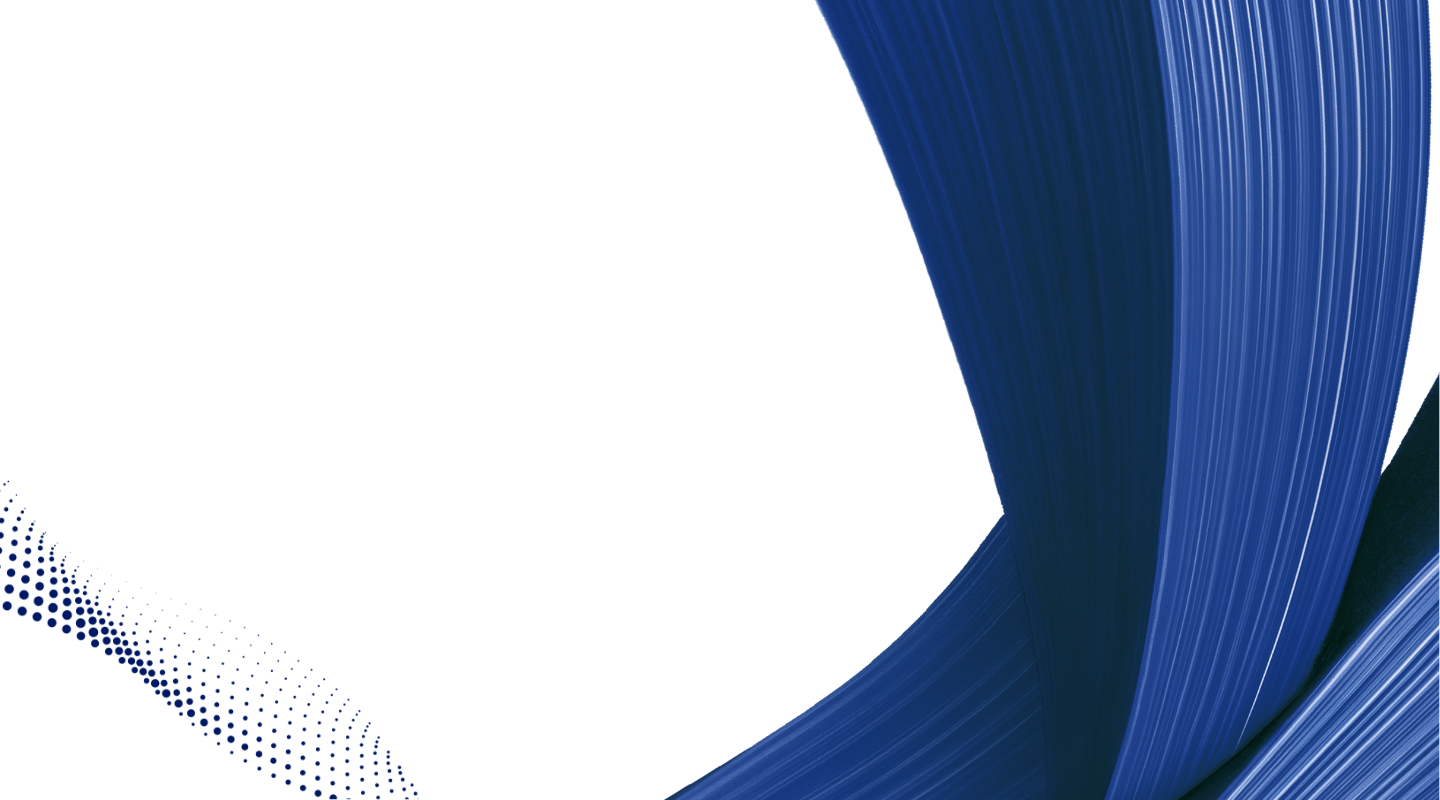

未来の価値とテクノロジーによる価値を組み合わせ、戦略から変革実行までのイノベーションを実現する未来価値創造戦略ユニット。ユニット長の橘知志は、10年前に「現場を知っていることの重要性」を痛感した経験を通じて、多種多様なバックグラウンドを持つメンバーで組成されるチームを築き上げた。「個社で解決できない課題をエコシステム全体で解決する」という哲学のもと、日本の産業構造そのものの変革に挑んでいる。
執行役員 プリンシパル
未来価値創造 戦略ユニット長
橘 知志
メーカー系SI会社を経て、アビームコンサルティングにキャリア入社。さまざまな業界向けにデジタル技術やデータを活用した新規事業開発、未来産業の構想、新サービス開発、デジタル基盤構築やDX人材育成などを多数実施。アビームコンサルティングのデジタル領域を立ち上げ時から主導。
「未来価値創造戦略ユニット」は、英語名では「Future Tech-value Innovation SU」と表記します。意図的に「Tech」という言葉を含めている理由ですが、前身となるIoTセクター時代から、テクノロジーの価値を見出し続けてきたからです。
また、「創造」は一般的に「Creation」と訳されますが、「作品を生み出す」「神による創造」など静的なニュアンスが強く、私たちが目指す未来の変革=イノベーションとは異なります。そういった理由から「Future Tech-value Innovation」にしました。私たちは「未来の価値」と「テクノロジーの価値」を組み合わせ、戦略から変革実行までのイノベーションを実現する、という想いをビジョンにも込めています。
未来の産業とテクノロジーを掛け合わせてトータルにデザインできる、競合優位性の高いコンサルティングファームとして、経営から現場までの価値創造の実現に貢献することが、未来価値創造戦略ユニット(以下、未来価値創造SU)が目指す姿です。

ビジネスをトータルデザインするためには、ビジネスとテクノロジーを掛け合わせた支援ができることが必要不可欠です。この掛け算を行いながら、経営だけではなく、現場の変革にも寄与することが重要であると考えています。
さらには、サービスの多様化が進む中で、常にクライアントの変化を捉え、柔軟に伴走支援を行うことを重視しています。
また、私たちのミッションの一つに「企業の自己変革」を掲げています。最終的には、クライアントが自分たちで自社を変革し続けられるようにすることがゴールです。もっといえば、産業が活性化され、自ら進化していくようになれば、我々の目的は達成されます。その時は私たちも新たなところでビジネス創出を支援していけば、未来へさらなる価値を残せると考えています。
日本の産業が強くなるためには、各社が努力し成長し続けることはもちろん重要ですが、これだけ環境変化が激しい時代においては、個社のみの努力には限界があると考えます。
では、どうするのか。私たちが重要視していることの一つは、デジタル時代ならではの産業集積をつくる、つまり「産業クラスター」の考え方です。
海外と比べて日本には、産業ごとに多くの企業が存在するのが特徴です。たとえば自動車業界でいうと、完成車メーカーが複数あれば、部品メーカーも多種多様な企業が存在しています。一方海外では、各産業で代表的な企業が決まっていることが多い。日本はそれが決まらないがゆえに前へ進まないこともありますが、各地でビジネスを推進している企業群の存在はチャンスでもあります。
例えば、自動車部品メーカーの集積地として知られている地域があるように、そういった産業集積地を現代版へアップデートしていく。地理的に点在する企業群をデジタルでつなぐことも視野に入れながら、もっと産業単位で企業を捉えて連携させていく必要があると考えています。
さらに、産業の垣根を越えた「地域エコシステム」も重要視しています。地域の産業活性化にもなりますし、働く人たちが実際に生活し、仕事をする中では地域経済が大切になってきます。地域を単位として、複数社でより良いまちづくりやエコシステム構築に携わっていく。産業クラスターと地域エコシステムは、私たちの思考を支える二つの軸だといえます。
アビームコンサルティング(以下、アビーム)の強みの一つは、あらゆる産業に対応できる「マルチインダストリー」体制にあります。インダストリーをまたいだ部署間の連携やコラボレーションが非常にフラットで、どのユニットでどのようなプロジェクトが進行しているかを把握し、それらを組み合わせることで新たな価値を創出することが可能です。
私たちがインテリジェンス組織として機能することで、クライアントに対してより幅広い情報やソリューションを提供できる体制が整っています。このような強みにより、クライアント個社への支援にとどまらず、地域全体のエコシステムに対しても、産業横断的な価値提供が可能になっています。
未来価値創造SUでは、次世代ものづくり変革、スタートアップ支援、循環経済など多様なテーマに他のビジネスユニットと連携しながら取り組んでいます。これらの取り組みに共通する価値軸が「データドリブン」であり、それこそが私たちの大きな強みです。
ただし、私たちが扱うデータには特徴があります。前身の部署がIoTに注力していたこともあり、「物や技術、時に空間から発生するデータ」となり、それらを組み合わせて活用していくことこそが未来価値創造SUのアプローチ方法です。
たとえば、海洋資源を活用したビジネスを考える時も、漁業者がいて、水揚げする港があり、魚自体のトレーサビリティがあり、一次加工を経て輸出に至るといったバリューチェーンの中で物とデータは絶えず動いています。意外に思われるかもしれませんが、伝統産業の分野でも同じことがいえます。中小・中堅企業の事業承継の課題でも技術やノウハウを後世に伝えていくために、デジタル化が欠かせません。
私たちが目指しているのは、こうした様々な領域の「物や技術」をデータで可視化し、利活用を図ることで新たな価値を創造すること。それこそが、産業や社会の未来につながる道筋だと考えています。
未来価値創造SUの強みの一つは、170名のメンバーのうち約半数が事業会社出身という、豊富な実務経験を持つ人材で構成されている点にあります。実は私自身、10年前にコンサルタントとしてものづくりの現場へ入っていこうと決めた時、全く太刀打ちできなかった苦い経験があります。そこで、現場のリアルな最前線を知っていることの重要性を再認識し、高い専門性を持つ事業会社出身者の方にも門戸を広げ、活躍機会を提供しています。コンサルタントとしての基礎力は入社後に鍛えられますし、それ以上に現場の知識を知っている人材のアドバンテージを活かしたい。そのため、現在も多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用しています。
実際に活躍しているメンバーは、それぞれが専門的な知識を有していますが、特定のスキルセットを尖らせつつも、複数部門を経験し、多様な環境で培われた柔軟性や多角的な視点を持っている人も多いです。一つのことだけを突き詰めてきた人もいますし、ジョブローテーションなどで複数の部門を渡り歩いてきた人もいて、多様な人材がいる組織といえます。

また、進化し続けるテクノロジーのキャッチアップも我々にとっては非常に重要なことであり、有効な手段の一つとして例えば海外イベントに出展し、そこで得た一次情報を詳細なレポートにまとめています。複数の海外の展示会に参加し、報告書として作成しています。これはお客様に見せても非常に高く評価していただけるレベルの情報源になっています。
また、未来価値創造SUのユニークなところは、国や政府機関、業界団体との連携において、現実的かつ実効性のある政策立案と社会実装も支援していることです。政府関係者の方々は国や業界の産業活性化に資する政策が作れる立場にあります。そこで私たちは、現場で起きていることを彼らにインプットし、より良い政策を形にしてもらうだけでなく、その社会実装の支援も私たちが行うという循環を作っています。この関わり方は民間のコンサルティングファームならではの役割だと思います。

未来価値創造SUでは、多様なバックグラウンドを持つ人材が「組み合わせの価値」を生み出すことが成功の鍵を握ります。3種類×3種類では9種類の組み合わせしかできませんが、5種類×5種類では25種類・・・というように多面的な価値創造が可能になります。
たとえば、スタートアップ支援をするメンバーがさまざまなイベントでネットワーキングをしている一方で、製造業に対して専門的な技術支援をするメンバーもいる。一見はバラバラに感じますが、この両者が連携することで、ディープテック系スタートアップに対してより深い支援が可能になる。ここでも掛け合わせの価値が発揮されるわけです。
コンサルティング業界を志望する方の中には、中長期的なキャリアパスの一つとしてスタートアップへの挑戦を考える方も多いと思います。私個人としては、その選択も含めて応援したいと考えています。実際に、未来価値創造SU出身者でスタートアップへ挑戦する人もいます。「うまくいかなかった場合は、また戻ってきても構わない」というスタンスで、人材の循環を促進しています。
志望者からは「事業会社とアビームの未来価値創造SUで迷っている」という話もよく聞きます。事業を担う側と支援する側という前提の違いはありつつも、私は「得られる機会の多さ」に差があることをよくお伝えします。事業会社の多くは単一のインダストリーに携わりますが、私たちは複数の業界や事業に対して支援ができる。そこは明確な選択肢として挙げられると思います。
5年先、10年先、20年先を見据えると、日本の産業は新しいステージに入っています。従来の産業の形は重要であり続けると思いますが、そこへ新しい世界観での産業の形を創造していく必要もあります。私たちは、クライアントと共に、そういった産業の形を作り上げていく役割を担っていきたいのです。
多様なバックグラウンドを持った人たちで組成された未来価値創造SUが、これからの産業や社会をどのように良くしていけるのか。自身の成長と合わせて、クライアントの成長、業界や産業振興などを実現していくことができる組織として、さらなる発展を目指していきます。