キャリア採用
障がい者採用
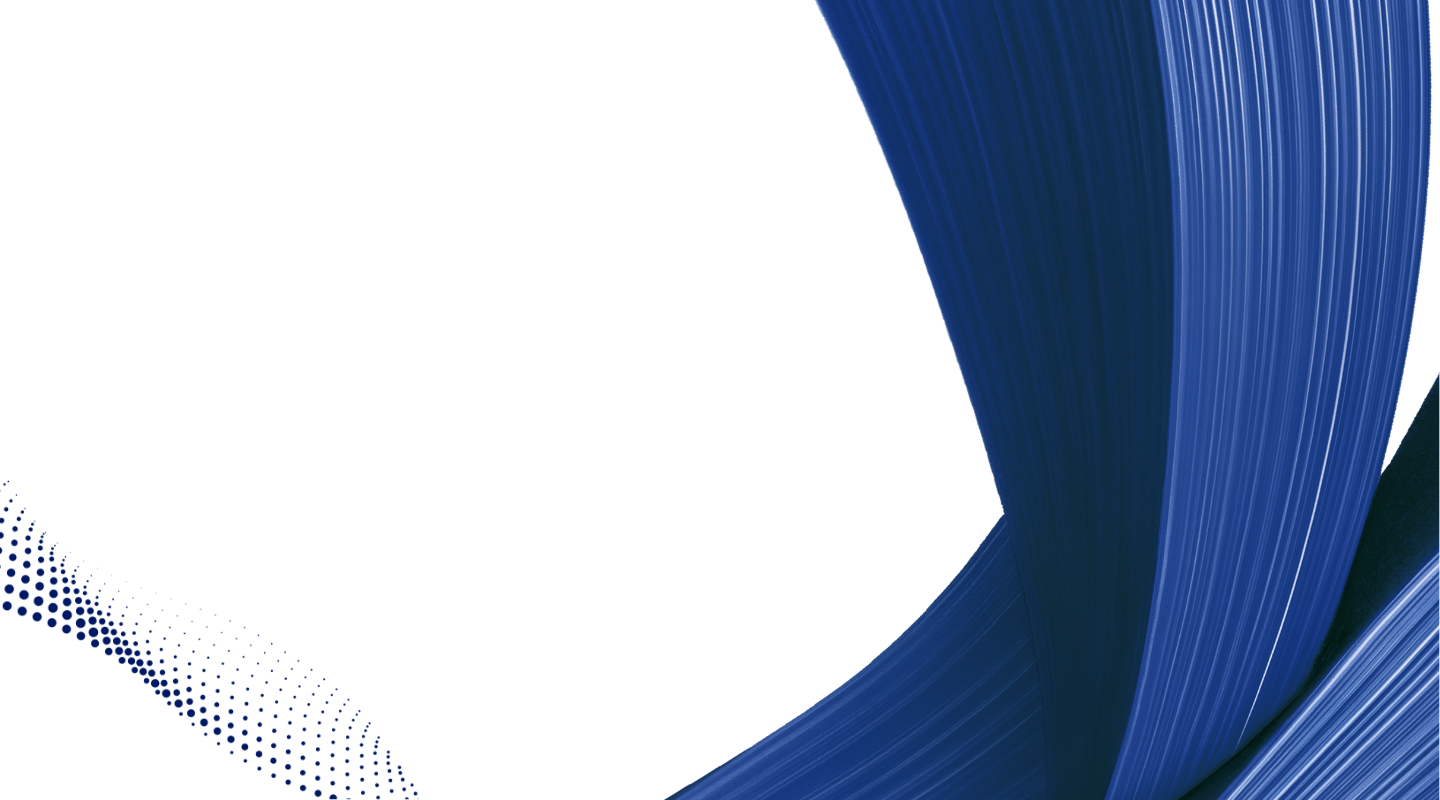

日本企業の低いPBRが問題視される中、アビームコンサルティングの企業価値戦略ユニットは「企業価値の向上」へのアプローチで変革をリードしている。「非財務と財務の統合」で実績を誇り、有識者と共に多くの先行事例を創出。企業価値向上のメカニズムに踏み込む同ユニットの使命と価値提供について、ユニット長の斎藤岳に聞いた。
執行役員 プリンシパル
企業価値 戦略ユニット長
兼 顧客価値 戦略ユニット長
斎藤 岳
新卒でコンサルティングファームに入社し、2001年アビームコンサルティングへキャリア入社。総合商社、情報通信業、サービス業、製造業、小売・卸業、独立行政法人といった幅広い業種に対し、戦略策定および戦略実現支援のコンサルティングプロジェクトを実施。また、認定プロフェッショナルビジネスコーチとして、戦略、リーダーシップ、チームマネジメント等の分野で、経営幹部/幹部候補生向けトレーニング講師を務める。
企業価値戦略ユニット(以下、企業価値SU)のミッションは、日本企業のPrice Book-value Ratio (≒企業価値)を世界水準まで引き上げることです。そのためには、企業価値向上のメカニズムに踏み込み、実現まで伴走する「企業変革パートナー」であることが重要です。
多くの企業が「サステナビリティ経営」や「資本コストを意識した経営」に取り組んでいますが、私たちは常に「企業価値の向上」という軸を持って、経営者や経営企画の方々と向き合っています。具体的には、「メリハリ投資」「資本コストと競争力を意識したマネジメント」「外部ステークホルダーとの共感」が実現できる仕組みを構築していくことです。

日本企業のPBRが低い理由は、大きく二つあります。
一つは、将来の成長性を株主に十分アピールできていない点です。隠れた魅力を持つ企業が多く存在する一方で、本来の企業価値をステークホルダーに適切に伝えられていないケースが多いと言えます。
もう一つは、資本コストに対して十分な利益を生み出しきれていない点です。これに対する解決策の一例として、事業ポートフォリオの再編があります。将来を見据えたとき、他社のほうが「ベストオーナー」となり得る事業については移管し、自社が成長すべき事業には集中投資を行うことで、その競争優位性を徹底的に高めていくという取り組みです。
こうした取り組みは、理論にとどまらず、企業内で合意形成を図った上で、着実に実現へと推進していきます。
戦略を提案して終わりではなく、描いた戦略が実現するまで責任を持ってやり切る。
それこそが、企業価値向上SUにおける、私たちの核心的な価値提供だと考えています。
企業価値SUが他コンサルティングファームと大きく差別化されている点は、「非財務と財務の統合」において業界でもトップクラスの実績を誇ることです。
この成果の源泉の一つには、弊社エグゼクティブアドバイザーである財務会計の有識者・柳良平氏の存在があります。ESGと企業価値の関連を示す計算式「柳モデル」を提唱される柳さんと、それを実践するアビームコンサルティング(以下、アビーム)のコンサルタントが二人三脚で、多くのクライアントと共に先行事例を作り上げてきました。
さらに、元オムロンCFOの日戸興史氏、元ソニーCHROの安部和志氏など、実際に日本企業の企業価値向上を牽引してきた方々をアドバイザーとして迎えています。
アドバイザーの方々が実際のプロジェクトにどの程度関与するのか、求職者の方からよく質問を受けることがあります。私たちの場合、定期的なコミュニケーションはもちろんのこと、アドバイザーにもプロジェクトに深く関与してもらいながら、一体となって進めています。
こうした実績ある経営者の知見・経験と、私たちの方法論を組み合わせることで、机上の空論ではない、実効性のある変革を実現しているのが、企業価値SUの特徴だといえます。
ESG経営やサステナビリティが注目される中、人的資本や知的資産などの非財務情報をいかに企業価値向上につなげるかが重要な課題となっています。私たちはこの課題に対し、「インパクト会計」という手法を用いて、将来的な企業価値向上を数値で定量化し、CSR活動や国際的な取り組みの効果も可視化しています。
「ポスト資本主義」の実現を検討しているというとわかりやすいでしょうか。非財務やESG指標が将来の企業価値につながるというメカニズムの検討が、資本主義のプラットフォームを前提としつつ、サステナブルな社会をつくる仕組みとなると考えています。
一つの好例として、製薬会社がAPACで蚊を媒介する病気に効く薬を無償配布した事例を挙げさせてください。CSR活動として評価されるにとどまらず、製薬会社の現地工場で働く従業員が自社に誇りを持つようになり、満足度の向上につながりました。その結果、離職率の低下や、安定したオペレーションによるコスト削減効果も生まれました。こうした取り組みが企業ブランドの向上を促し、長期的視点を持つ投資家からの資金調達にも貢献するという好循環が生まれたのです。
同様に企業価値SUでは、企業価値向上の重要なドライバーになっているメカニズムを明らかにし、一見すると直接的ではない活動のうちどこのインパクトが最も大きいのかを見定めた上で、集中投資していくというマネジメント支援を行っています。
また、2025年8月には企業共創型コンソーシアム「Impact Value Consortium(IVC)」を設立しました。日本のトップ企業と連携し、インパクト会計のデファクトスタンダードを確立することで、活用促進を目的としています。アビームが持つ様々な業界での実績をもとに、業界特性に応じたアプローチを構築して、それぞれの企業が持つ固有の強みを最大限に活かせる仕組みにしていきたいと考えています。
企業価値SUは、戦略と実行を一体であると捉え、実現可能な戦略を描き切るということが特徴です。期待されているのは経営と現場と投資家をつなぐ役割。メンバーのキャリア設計においても、CFOやFP&Aのように経営者から相談されるコンサルタントや、あるいは自ら起業家を目指すといった道も拓けています。
競争優位を特定して数値的にもインパクトがあることを検証しながら戦略を描き、また戦略からその経営管理の数字に落とし込んでいく。それぞれの領域を自由に行き来できるメンバーが育っています。やはり、企業価値SUには、企業価値向上のメカニズムや数字に強く、かつ戦略を描ける人材がいることが大きな強みです。特に「非財務が5年後の将来にどう効くのか」という統計的な処理を含めてできる人材が戦略を策定できるところは、私たちの独自性だと考えています。

分かりやすい例として、マテリアリティ(=企業が優先して取り組むべき「重要課題」)の見直しがあります。クライアントの長期ビジョン実現に向けて、経営目標指標や現場で重要視する活動指標を見直したものです。現場の指標がビジョン実現に結びつくメカニズムを明らかにすることで、経営目標が単なるお題目にならないように見直すことが大切なのです。
私たちが戦略策定だけでなく実行までこだわりを持っているのは、アビームの戦略チーム全体の特徴でもあります。クライアントからよく評価いただくのが、「クライアントと同じ目線で考え、地に足の着いた提案を常に心がけてくれている。そのため、実際に企業価値が上がり、利益も出る戦略を考えてくれて、実行もできた」という点です。
私がメンバーに常々伝えているのは「想像力」の大切さです。相手の話を聞いた時に、言葉の裏にある背景まで理解できる想像力があると、その会社や担当者の状況、それらのコンテクストを加味した上で、納得感あり実行可能な提案ができるのです。簡単にいえば、常に相手志向で、相手の気持ちに立って考える、ということです。
また、チーム全体のスキル向上を図る上では、企業価値SUが手がけた実際のプロジェクトで得た体験の共有を重視しています。特に、各プロジェクトにある「課題を突破した瞬間」の経験事例は、いかなるプロジェクトでも起こり得るため貴重です。アウトプットを見ただけでは分からない、こういった実体験に基づくナレッジはコンサルタントとして成長するためにも大きな学びになるのです。

私が約30年間、コンサルタント業界で仕事を続けているのは、この仕事がシンプルに面白いと考えているからです。戦略領域のプロジェクトは3カ月から半年の短期プロジェクトが多いですが、企業価値SUが価値発揮する領域は企業価値を実際に上げていくことであり、1〜2年で結果が出るものばかりではなく、少し長い時間をかけないと分からないことが多いです。ただ、数年後に実際に会社が大きく変わっていくのを目の当たりにすると、この仕事に関わることの重要性を感じます。
過去に私が携わった案件で、ある地方のメーカーで経営管理の仕組みを変革したプロジェクトがありました。実施当初は売上が微減したものの利益は毎年向上し、十数年後にその土地を訪れてみると、地域全体が活性化していました。当時のプロジェクトメンバーが協力会社にも同様の取り組みを展開したことで、企業体質の改善につながり、結果として地域全体を支える土台にもなりました。
こうした長期的なスパンで見ると、私たちの仕事は企業や社会に大きなインパクトをもたらす可能性があるわけです。これから一緒に仕事をするみなさんにも、企業価値向上という社会的に意義深いテーマに取り組める面白さを感じていただきたいと思います。
統合的思考、統計解析、経営戦略などをシームレスに結び付ける能力が重要で、なおかつ知的好奇心も欠かせません。一つの専門分野だけでは私たちのチームのミッションは達成できないからです。ミッションやビジョンから戦略、統計解析までを全てをつなげていくことができる、何にでも興味を持って学び続けられる方に来ていただきたいと思っています。