キャリア採用
障がい者採用
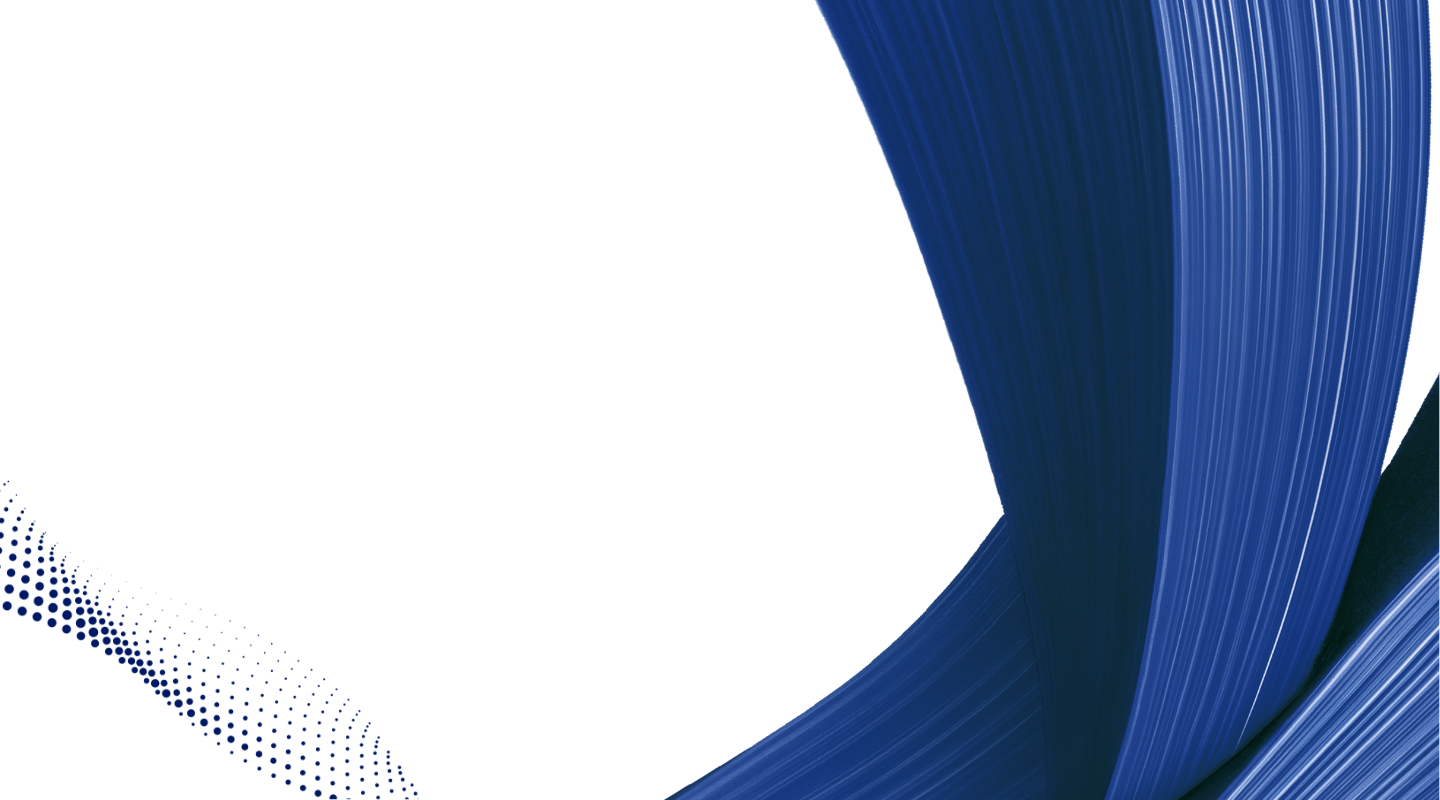

生成AIの台頭から既存システムのモダナイゼーションまで、企業のデジタル変革は複雑さを増している。特定の技術やソリューションに固執せず、クライアントにとって最適なデザインとアーキテクチャを総合的に判断する──デジタルテクノロジービジネスユニット design X architectセクターは、プロジェクトの実働と未来への研究を両立させる独自の組織運営を実践する。セクター長の安藤裕介に、 design X architectセクターが企業変革にもたらす価値や組織の有り様について聞いた。
ダイレクター
デジタルテクノロジービジネスユニット
design X architectセクター長
安藤 裕介
金融・小売・製造・公共など、幅広い業界で新規事業の立ち上げ、業務改革、システム導入を支援。ビジネスとITの両面から計画を策定し、段階的に実現する手法や、柔軟に進めるアジャイル型アプローチを強みとする。近年は、デジタル技術を活用した事業創出や人材育成にも注力。社内では、独自の方法論を開発・展開する全社イニシアティブのリーダーを務め、重要プロジェクトの品質管理にも携わっている。現場と経営の双方に価値をもたらす変革の実現を目指し、特定の技術や手法に依存せず、状況に応じて最適アプローチを追求・実践・啓発し続けている。
design X architectセクターを一言で表現するなら、それは企業のデジタル化における「総合診療医」です。「デザイン」と「アーキテクチャ」という、一見相反するようにも思える概念を組み合わせた組織名には、明確な意図があります。「デザイン」は、事業デザインからユーザー体験、アプリケーション、さらには技術設計に至るまで、幅広い領域を包含する概念です。一方で「アーキテクチャ」は、それらのデザインを実現・駆動するための組織、ビジネス、システムの最適解を追求するものであり、システムやソフトウェアの基本設計や構造を指します。design X architectセクターは、これら両面のアプローチを徹底的に追及する組織です。

例えば、医師に内科や外科といった専門分野があるように、多くの企業もそれぞれの専門領域に特化し、高度なソリューションを提供しています。その中で、 design X architectセクターは「企業のデジタル化」における総合診療医のような存在でありたいと考えています。「組織の文化変革に取り組みたい」「データを活用した新規事業を始めたいが、何から着手すべきかわからない」「数千人規模のプロジェクトで業務改革とシステム変革を同時に進めたい」――このような抽象度の高い課題に対して、ビジネスやサービス全体をデザインする力とシステムのアーキテクチャ力を掛け合わせ、ビジネスデザインや業務モデリング、最適な技術の組み合わせまで、企業にとって本当に必要な手段を選び、生み出します。たとえ社内に実績がないソリューションであっても、クライアントにとって最善であれば、ためらうことなく提案します。
時には、表面的に認識されている課題の背後に、真の原因が潜んでいる場合もあります。その場合には、「実は根本的な原因は別のところにあるのではないか」と、真の課題を見極めて指摘していきます。また、クライアントが抱える漠然とした悩みや不調をきっかけに、「健康体であり続けるために何をすべきか」といった予防医療的な観点からの提案を行うこともあります。また、「これではいけない・・・」と理解していながらも、人や組織の壁、過去の成功体験、変化への不安や恐れ、目先の対応に追われ、変革の一歩を踏み出すのが難しい経営層や事業責任者の行動を後押しすることもあります。そうして、企業にとっての「総合診療医」として、課題に応える役割を果たしたいと考えています。
現在、多種多様な先端テクノロジーが目まぐるしく進化する中、多くの企業には、この急速な変化に適応することが求められています。一方で、こうした変化に適応するための準備に着手できている企業は、決して多くないのが現状です。そこで、私たちは、優れたデザイン力、アーキテクチャ設計力、そして未来を描くアプローチによって、企業変化対応力を高め、テクノロジーによる変革の波に柔軟に適応できる組織への転身を支援しています。デジタルエンタープライズの未来に向けた戦略立案・実行、そして運営の変革に至るまで――。その全体像を構想し、具体的なロードマップとして描き、実現をサポートすることが私たちの使命です。
そのような私たちの使命を果たすために、私が重要視しているのは、テクノロジーとビジネスを「翻訳する力」です。技術の専門家は、技術的な側面に焦点を当ててコミュニケーションを取ることが多いものですが、コンサルタントであれば、その技術がビジネスにどのような価値をもたらすのかを、経営の視点から分かりやすく説明することも求められます。例えば、「なぜその技術が今、最適な選択肢なのか」という問いに対しては、単に技術的なメリット・デメリットを説明するだけでは不十分です。クライアントのビジネス状況を踏まえたうえで、競合や市場環境、中長期戦略との整合性をもって根拠を提示することが、信頼を得るうえで非常に重要です。
実際、私は2000年頃から「アジャイル」という言葉の使用を控えていました。アジャイルとは、変化に迅速に対応し、継続的に価値を提供する開発手法ですが、この言葉が広まるにつれて、手法そのものが目的化してしまい、「スクラムマスターがいればよい」「アジャイルだからこうすればよい」といった形式重視の誤解が広がるケースが多く見受けられました。しかし本来、アジャイルの本質は、クライアントに早く価値を届け、改善を重ねていくという原則にあります。大切なのは、「なぜそれが良いのか」を深く理解することから始めることです。「ビジネス効果につながらなければ意味がない」という考えのもと、私たちはこうした技術の言葉を正しく“翻訳”し、価値ある提案へと変換することを大切にしています。それこそが、デザインとアーキテクチャの両面から支援できる、私たちの最大の価値だと考えています。
design X architectセクターでは、旺盛な好奇心と、常により優れたものを追求する学習意欲を原動力に、複数の専門スキルを活かして独創的なアイデアを生み出す「タコ型人材」を重視しています。私たちは、組織的な支援と協働を通じて、こうしたタコ型人材の力を最大限に引き出し続けることを目指しています。
なぜタコ型人材を重視するのか。それは、多様なスキルを持つ人材が非常に貴重である一方で、企業内ではその能力を十分に活かしきれていないという現状があるからです。実際、「プロジェクトで問題が発生したため状況整理をお願いしたい」「どの部門でも解決できない課題があり、判断を仰ぎたい」といった、いわゆる“火消し役”として依頼を受ける場面が少なくありません。
こうした人材は、プロジェクトや事業の成功において極めて重要な役割を果たしています。「関係者間の調整」や「複雑な課題の整理」など、単に複数の技術や知見を持つだけでなく、ビジネスを円滑に進めるために不可欠なファシリテーションや意思決定支援といったスキルでも、多くの成功事例を陰で支えているのです。

さらに、タコ型人材は「未来の技術」や「未だ実用化されていない技術」を見出す力に長けており、業界やテクノロジーを横断して応用可能な理論やセオリーを提唱するなど、他にはない特性を持っています。このように多様な部署で活躍できる希少な存在でありながら、その能力開発は多くの場合、個人の自主性に委ねられているのが現実です。
しかし、ビジネスやテクノロジーが日々進化する現代において、未来の方向性を考え続け、様々な事例を収集・分析し、新たな提案へとつなげる活動は、企業価値の向上においてますます重要な役割を果たすと私たちは考えています。そのため、design X architectセクターでは、タコ型人材の育成と強化を目的とした研究開発活動に積極的に取り組んでいます。通常のプロジェクトにおいても、従来以上の品質と生産性を追求しながら、未来志向の研究や手法の改善、クライアントへの価値提供パターンの体系化に取り組むことを、私たちのミッションの一つと位置づけています。

design X architectセクターでは、上司の指示を待つのではなく、自ら判断し行動する自発性を重視しています。逆ピラミッド型の組織運営を取り入れ、マネージャー層は挑戦の機会を作り、リソースを確保しながら、関係者との合意形成を図り、プロジェクトを共に推進していく役割を担っています。
現場で何が価値を生むのかを最も理解しているのはメンバー自身です。そのため私たちは、メンバーの好奇心や専門性に基づいて、「今のトレンド」「取り組みたいテーマ」「クライアント課題への解決策」などを対話する機会を定期的に設けています。
design X architectセクターの文化は、価値ある提案を自ら行い、全員でフォローするスタイルが浸透しています。プロジェクトの合間にも、仕事の質とスピードを高め、余白の時間を新たな取り組みに充てる工夫が奨励されています。将来的には、各専門分野のAIエージェントとタコ型人材が協働する仕組みも視野に入れています。リアルタイムで知識にアクセスできる環境が整えば、個人の能力は大きく引き上げられ、クライアントへの貢献もさらに強化されるでしょう。
こうした未来に向けて重要なのは、「一人で全てを担う必要はない」という考えです。私たちは、チーム全体でエキスパートジェネラリストとして機能することを目指しています。たとえ専門性が限定的でも、他者貢献の意志があれば、仲間と協働することで大きな価値を生み出せます。
クライアントにとって最適なデザインとアーキテクチャを提案し、未来を共に描く。それを支えるタコ型人材の力を、組織の支援と協働によって最大化し続ける。そうした探究心あふれる環境を、これからも大切にしていきたいと考えています。