キャリア採用
障がい者採用
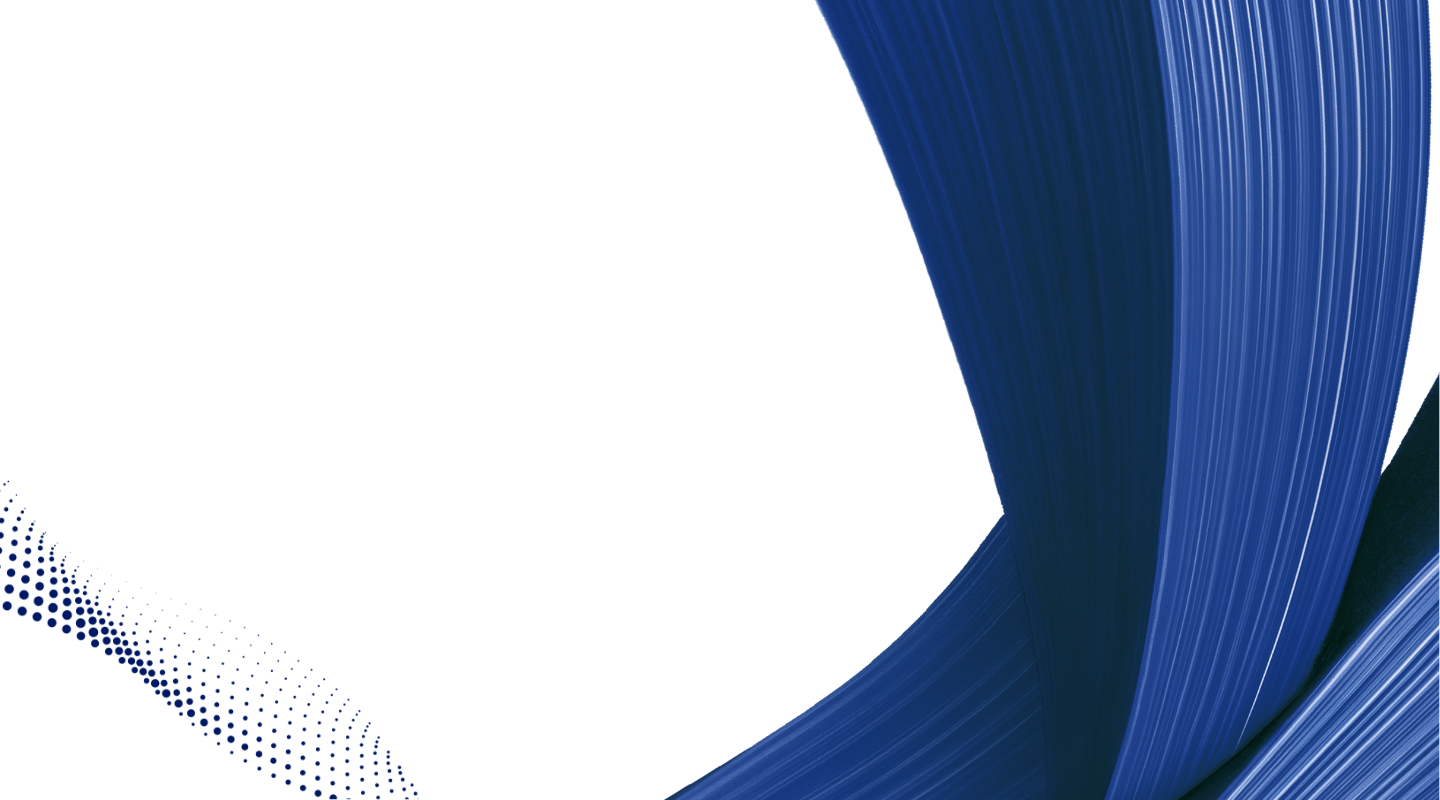

クラウドテクノロジーとサイバーセキュリティの領域で、企業の変革構想とその実現を技術力で支える。デジタルテクノロジービジネスユニットのAdvanced Cloud Technologyセクターは、デジタルテクノロジーによる変革を組織に浸透させ、その効果を着実に実現する伴走支援を提供している。エンジニアからコンサルタントへ転身し、現在は同セクターを率いる内田康介セクター長に、アビームコンサルティングならではの「変革実現力」について聞いた。
プリンシパル
デジタルテクノロジービジネスユニット
Advanced Cloud Technologyセクター長
内田 康介
2001年に新卒でアビームコンサルティングへ入社。クラウドおよびセキュリティ領域に関する高い専門性と、幅広い知識・経験に基づくITコンサルティングサービスを提供。戦略策定、アセスメント/デューディリジェンス、アーキテクティング、大型デリバリー/モダナイゼーション、セキュリティ対策、組織改革・統制等、業種を問わず幅広く支援する。2015年から5年間は米国に駐在し、日系企業を中心に各種支援を実施。2023年度より、デジタルテクノロジービジネスユニット Advanced Cloud Technologyセクター長として、組織リードおよび事業拡大に取り組んでいる。米国公認会計士の資格を有する。
Advanced Cloud Technologyセクター では、クライアントへの継続的な価値提供を目的に、サービス領域を大きく5つに分けて展開しています。具体的には「Strategy & Architecting」「Cloud Native Integration」「Cloud Data Platform」「SAP on Cloud」「Cyber/Cloud Security」と領域を定め、クライアントの状況やニーズ、さらには技術動向を的確に見極めながら、質の高いコンサルティングサービスを提供できるケイパビリティを構築しています。
クラウドテクノロジー領域においては、AWS、Microsoft Azure、SAP Business Technology Platformといったハイパースケーラーが提供する多様なサービスを企業内でいかに効果的に組み合わせ、活用し、変革構想と実現に寄与していくかという点にフォーカスしています。より難易度の高いミッションクリティカルなシステムへの本格的なクラウドリフト/シフトが進む中で、単にそのテクノロジーを適用するだけでは真の変革は実現できません。今後の技術や人材の動向も踏まえ、戦略的なクラウド利活用とモダナイゼーションの推進に関する支援をしています。

一方で、クラウドをはじめとしたテクノロジーの利活用が進むほど、ビジネスは高度化・多様化したサイバー攻撃に晒されるリスクが高まります。多くの企業・組織にとって非常に大きな脅威となっており、この環境下では、セキュリティ戦略および各種施策を実際のIT環境・組織・プロセスにどう落としこみ、実現していくかが重要です。また、策定したポリシーや施策が、現場で適切かつ着実に運用される状態を維持することも求められています。こうしたニーズに応えられるのは、クラウドとセキュリティを一つの組織で統合的に推進しているAdvanced Cloud Technologyセクターならではの強みであり、まさにアビームが誇る「一気通貫の提案力」が発揮される領域と言えます。
私がこの仕事で最も大切にしているのは、テクノロジーを起点にクライアントの「真の困りごと」や「本当にやるべきこと」を見極めたうえで、解決策を提案し、具体的にビジネスを創っていく過程をリードすることです。
例えば、クラウド領域におけるモダナイゼーションでは、クラウド化、マイクロサービス化、DevOpsの導入といった技術の適用自体が目的化してしまうケースがあります。一方で、既存システムの暗黙知や組織内の事情に引きずられ、「現状+α」で十分だとする保守的な考えに陥ることも少なくありません。もちろん新技術のメリットを享受することや、現実的な期間や予算の範囲で成果を目指すことも重要ですが、本来の目的はモダナイゼーションの目的達成のために何をどこまで行うべきかを、組織固有の文化や経緯にとらわれずロジカルに考え抜くことにあります。

特にミッションクリティカルな仕組みでは、技術面だけでなく組織内の力関係やしがらみといった極めて人間的な要素も考慮しながら推進していくことが必要です。思い切ってクライアントの懐に入り込み、第三者の視点から本質的な解決に導くことこそ、コンサルタントとしての価値だと考えています。
サイバーセキュリティ領域における私たちの仕事は、一種の社会課題解決への挑戦だと捉えています。中堅・中小企業や地方に拠点を持つ企業、医療機関・教育機関などの組織においては、大手企業に比べて予算が限られ、またセキュリティに知見のある人材を確保すること自体が困難です。セキュリティ確保の重要性を理解していても、それぞれの事情によって進められない現実もあります。そうした組織に対しても真摯に向き合い、利害関係者を巻き込みながら、企業/組織の枠を超えてリーズナブルで実現可能なソリューションを提供する枠組みを作り、主導することに向けた取り組み・推進支援を行っています。こうした取り組みを通じて、企業グループ全体、ひいては日本企業全体のセキュリティ水準の向上に貢献したいと考えています。
そのために私は、クライアントやステークホルダーから日々小さな「なるほど」を引き出すことを意識しています。「確かに」ではなく「なるほど」と言ってもらうためには、担当者の立場や状況、経緯、時には社内の対立関係まで含めた背景を地道に整理し、それらを踏まえて徹底的に考え抜き、相手に応じたロジカルなコミュニケーションを行うことが欠かせません。自分の仕事に誇りを持ち、クライアントとともに日々奮闘し、信頼を築き、成果を実感することが、コンサルタントとしての醍醐味だと思っています。

テクノロジーやソリューションが多様化・複雑化する現在、企業が継続的に価値を創出していくためには、それらを適切に活用することが不可欠です。
そのため、今後も複合的な専門性が求められる傾向は続くと考えられます。例えば、AWSやMicrosoft Azureに精通した専門家は多くいますが、両方を熟知している方や、セキュリティに通じながらGoogle Cloudの知見を持つ方など、横断的に理解できる人材は限られ、そのことが付加価値・差別化要因ともなり得ます。そのため、コンサルタントである以上、好奇心を持ち、常に学び続ける姿勢が欠かせません。
テクノロジーを専門とする中で、特定の技術を極めるスペシャリスト志向も重要ですが、多くの企業では複数のソリューションやテクノロジーを組み合わせたシステム群を構築・活用しています。そのような環境において課題に向き合うには、新旧様々な技術要素を的確に把握し、あるべき姿を構想し、実現まで主体となって導く力──本質を見抜く力、幅広い知見、柔軟な対応力が求められます。
クライアント以上にクライアントを理解し、最適解を導くための変革構想・変革実現力を備えた組織を目指し、Advanced Cloud Technologyセクターでは、複数の専門領域を横断して知識の高度化とそれらを具備する人材が状況に応じて適宜連携できる組織体制を構築しています。5つの領域ごとに近い志向を持つメンバーをグルーピングし、情報・知見の共有や技術議論を日々重ねることで、メンバー相互に学びを深め、応用力を高めています。
さらに、高い実現力を持つ人材の育成と強化にも注力しています。クラウドやセキュリティに関する資格取得を積極的に促進し、インセンティブを設けることで学習意欲の維持・向上を支援しています。ハイパースケーラーやサイバーセキュリティ団体が主催する海外カンファレンスへの参加機会も提供し、最新のテクノロジーやソリューションの「熱気」に触れながら、要素技術を理解・吸収する環境を整えています。
現在、非常に多くの案件をご相談いただいており、人材の確保が急務となっています。複雑化するニーズに対して、多様な視点を持ち、要素をつなぎ合わせて課題をハンドリングできる人材を求めています。採用において最も重視しているのは、「クライアントの前にプロフェッショナルとして立てるかどうか」。これまで身につけてきた技術的な知見そのものも重要ですが、より高いパフォーマンスを発揮するために自らを磨き続ける意欲・意識があるかどうかはコンサルタントであるための必須要件だと考えています。また、現実の環境や制約、利害・人間関係の中で如何に最適解を導くか、それに向けてクライアントの思いを汲み取り、その場にふさわしいコミュニケーションスタイルでロジカルなやり取りができること、あるいはそのポテンシャルが感じられるかどうかを見極めています。
目に見えず、物理的にも触れられないITシステムやソリューションをもって企業にどのような価値をもたらすか。その特性が変わらない限り、コンサルタントに求められる資質も変わらないと考えています。私自身がITに出会ったのは小学生の頃。初めて自作プログラムが正しく動いたときの感動は、今でも鮮明に覚えています。テクノロジーを通じて課題を解決し、誰かの役に立つーーその小さな感動の積み重ねこそが、この仕事の醍醐味です。大きな成果は年に数回かもしれませんが、日々の自己成長と「なるほど」の積み重ねを大切にしながら、メンバーとともに新たな価値創出に挑み続けています。